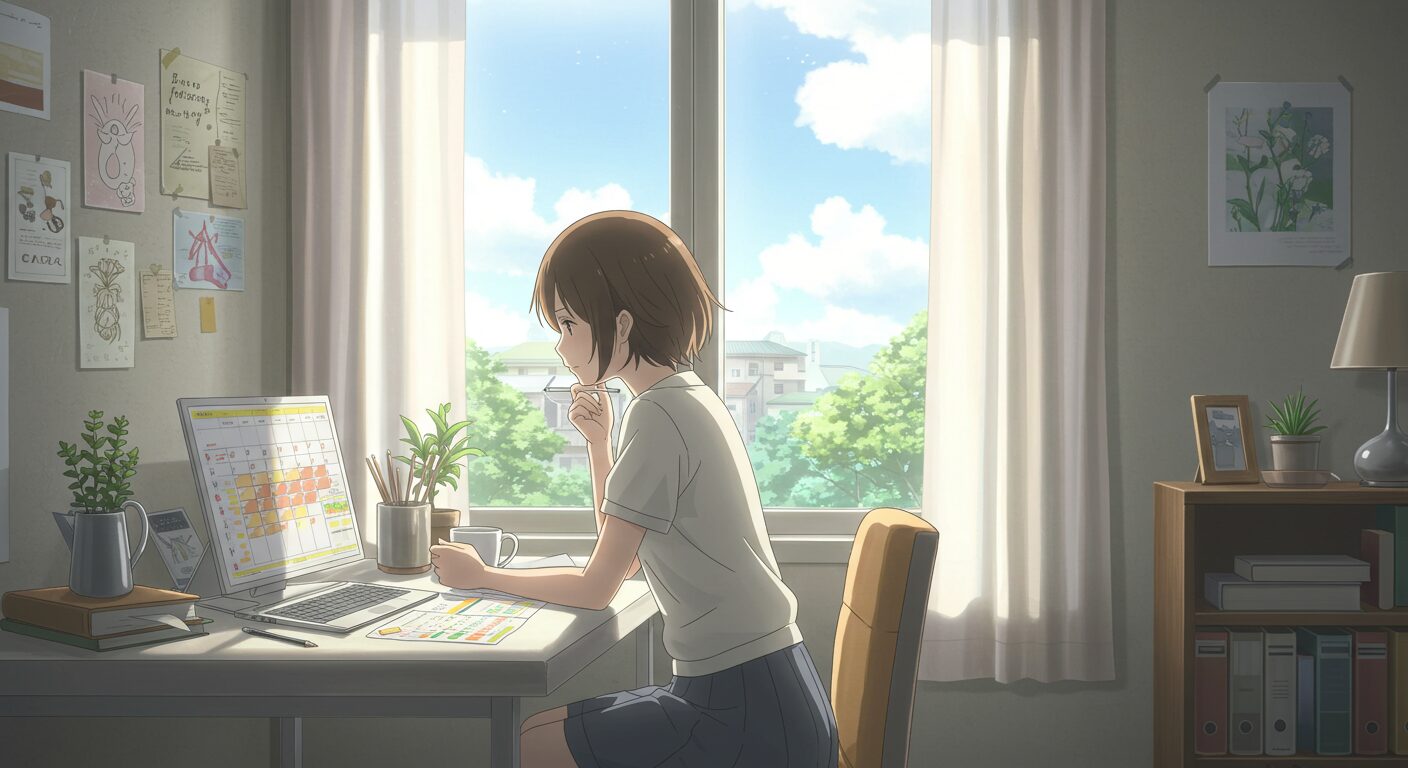習慣って何日くらい続けたら身につくのかな? 3日坊主の私でもいける方法ないかなあ…



平均で66日っていうデータがあるんだって。でも、人によって全然違うらしいよ



えっ、そんなに? てっきり1ヶ月くらいかと思ってた…それじゃ続かないかも…



大丈夫。大事なのは、気合より「しくみ」なんだって。ちゃんと自分に合ったやり方で続ければ、意志が弱くても習慣になるって話だよ
習慣づくりと聞くと、つい「強い意志」や「根性」を思い浮かべてしまいがちです。
でも実際には、習慣が身につくスピードも方法も、人によって驚くほど違います。
この記事では、科学的な調査データをもとに習慣になるまでの平均期間と仕組みで習慣を定着させる方法、さらに、わたしがしゅうかんかのためにふだんやっていることについてもまとめてみました。
がんばりすぎなくても習慣づくりが続けることができると感じてもらえたら嬉しいです。
- 習慣が身につくまでの平均日数
- なぜ人によって習慣化にかかる期間が違うのか
- 平均日数を気にしすぎると逆にうまくいかない理由
- 習慣を続けやすくするための現実的な工夫や考え方
習慣になるまでの期間はどれくらい?


- 研究による習慣になるまでの平均日数
- 人によって違う!習慣化にかかる日数のばらつき
- 日数を気にしすぎると失敗する理由
研究による習慣になるまでの平均日数
「習慣になるまでにはどれくらいの時間がかかるんだろう?」と気になる人は多いと思います。
何日続ければ「もうこれは習慣になった!」と実感できるのでしょうか。
ここでは、実際に行われた研究や調査をもとに、習慣が定着するまでの日数の平均値をまとめてみました。


習慣化するまでの平均日数は「66日」
習慣が身につくまでの平均日数は「66日」とされています。
これは、ロンドン大学の研究チームが発表した調査結果によるものです。
彼らは96人の被験者に、新しい行動(運動・食生活など)を日常に取り入れてもらい、行動がどれくらいで「自動化」されたかを調べました。
その結果、習慣として定着するまでにかかった平均日数が66日だったのです。
ロンドン大学の研究チームが発表した研究
How are habits formed: Modelling habit formation in the real world – Lally – 2010 – European Journal of Social Psychology – Wiley Online Library
習慣にしたいことの種類で日数は変わる
ただし、すべての習慣が66日で定着するわけではありません。
行動の内容によって負担の大きさが異なるからです。
たとえば、「水を一杯飲む」「歯を磨く」など簡単な行動なら20日ほどで習慣化するケースもありますが、「30分の運動」「毎日読書」など少し頑張りが必要な行動は80日以上かかることもあります。
上記の研究結果でも、習慣化にかかる期間には18日〜254日と大きな差があったと報告されています。
平均はあくまで目安にしかならない
平均66日という数字は参考になりますが、自分も同じくらいで習慣になるはずと思い込むのは少し危険です。
人それぞれ生活リズムや意志力、モチベーションに差があるからです。
「できるだけ早く身につけたい」と焦るよりも、「このくらいの日数を目安に、マイペースで続けよう」と考えた方が、無理なく続けられます。
私が66日続ければ習慣になると信じてあることを続けたとしましょう。
66日後、もしそれが習慣になっていなかったとしたら、これまで続けてきたのは何のためだったのかと落胆するはずです。
こんなことにならないためにも、平均値はあくまで参考資料として捉えておきましょう。



私も習慣化を始めてすでに66日以上経過していますが、まだ習慣化したと感じるところまではいけてません。
人によって違う!習慣化にかかる日数のばらつき
「平均66日」と聞くと、「じゃあ自分も2ヶ月くらいで習慣にできるかな」と思いがちですが、実際はそう簡単にはいきません。
先ほど少し触れましたが、平均日数はあくまでも目安。
習慣化にかかる日数には、かなりの個人差があります。
ここでは、なぜ人によって日数に差が出るのか、どんな要素が影響しているのかをまとめていきます。


習慣化は性格によってスピードが違う
習慣が身につく早さは、その人の性格や考え方に大きく影響されます。
たとえば「コツコツ型」で地道に続けるのが得意な人は、比較的早く習慣にできることが多いです。
反対に「気分屋さん」や「飽きっぽい」と自覚している人は、途中でやめてしまうこともあるので時間がかかる傾向があります。
習慣化にかかる時間は、その人の性格やモチベーションのタイプ次第なのです。
環境や生活リズムも大きく関係する
また、生活の中で習慣を続けやすいかどうかも重要なポイントです。
たとえば、忙しくて毎日同じ時間に行動するのが難しい人や、子育て・仕事で予想外のことが起こりやすい人は、習慣が定着しづらくなります。
一方で、ルーティンがしっかり決まっている人は、そこに新しい行動をうまく組み込めるため、習慣化がスムーズに進みます。
習慣の身につき方は「生活のしやすさ」にも左右されるのです。
得意・不得意も影響する
さらに、行動そのものとの「相性」も無視できません。
たとえば、読書が好きな人なら「毎日10分読む」ことはすぐに習慣になりますが、苦手な人にとってはハードルが高く、何度も挫折するかもしれません。
このように、「自分にとってやりやすいかどうか」も習慣になるまでの日数を左右します。
だからこそ、他人の成功例をそのままマネするだけではダメなのです。
最初はマネからスタートするのはいいですが、それを少しずつ自分に合ったやり方に改良していく必要があります。



好きなことなら頼まれなくても勝手に習慣になってしまうかも
日数を気にしすぎると失敗する理由
「あと〇日続ければ、習慣になるはず!」とカウントしながら頑張るのは、一見前向きな方法のように思えます。
でも、この日数を気にしすぎるやり方は習慣化を失敗させてしまう落とし穴になることがあるのです。
ここでは、その理由とどう考え方を変えればうまくいくのかをまとめてみました。
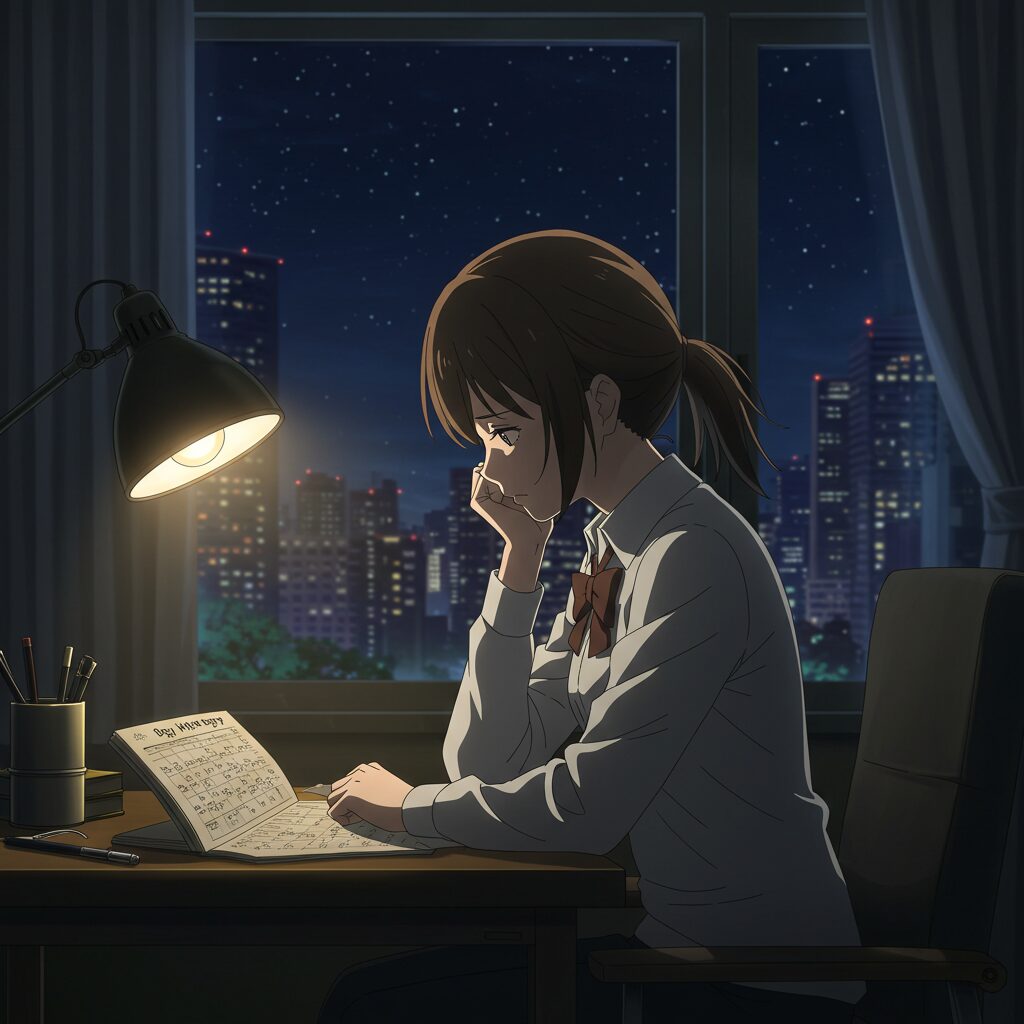
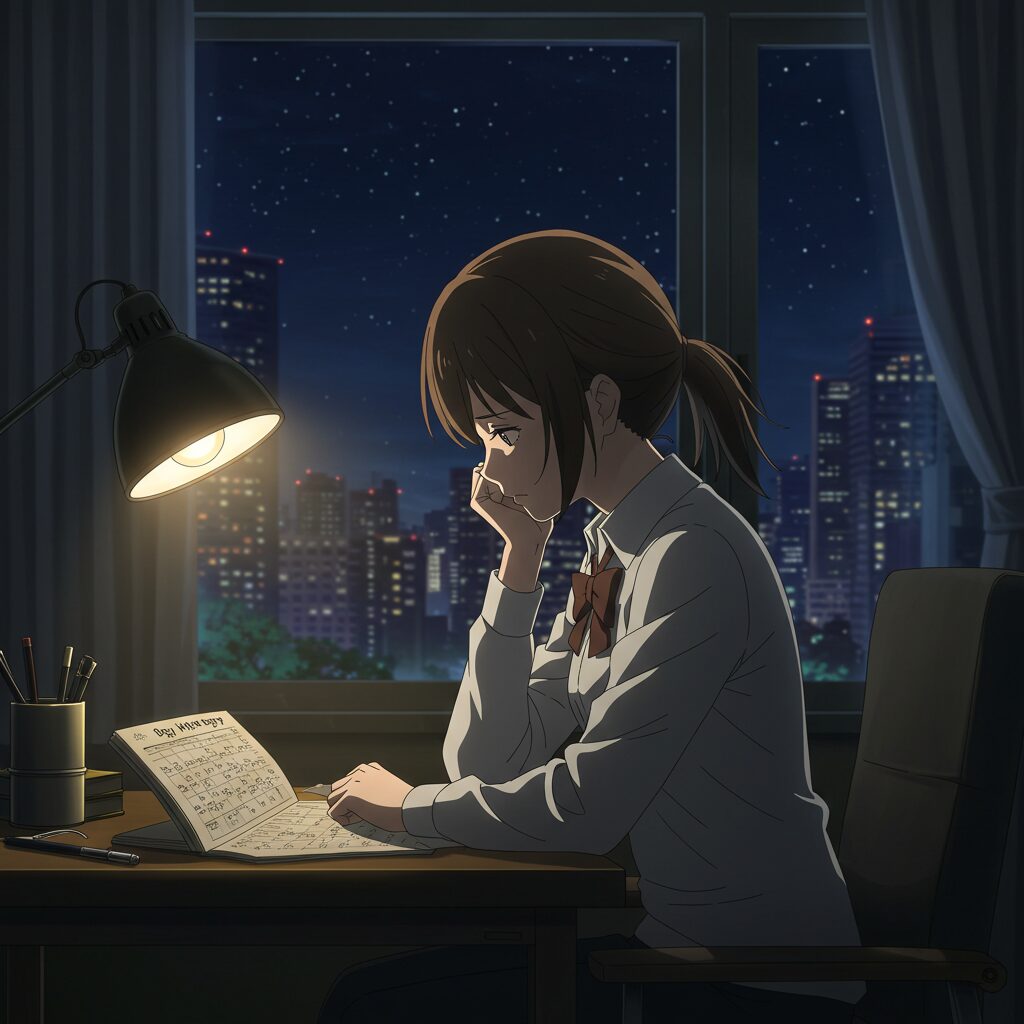
日数がゴールになると心が折れやすい
「何日やればOK」とゴールを決めすぎると、続けることが目的ではなくなってしまいます。
たとえば「30日続ければ習慣になる」と信じて頑張っていた人が、29日目にサボってしまったらどう感じるでしょうか。
「全部ムダになった」「もう意味ない」と思ってやめてしまうケースもあります。
このように、日数をゴールにすると、その日数が崩れたときのダメージが大きくなってしまうのです。
習慣はいつの間にか身につくもの
そもそも習慣とはどんな状態になることでしょうか。
これをやろうと意識しなくても自然とできるようになる状態のことです。
だから、「何日でできるようになるか?」にばかり意識を向けると、本質を見失ってしまいます。
大切なのは、気づいたらやるのが当たり前になっていた、という状態を目指すこと。
そのためには「今日は何日目か」よりも、「昨日と同じように今日もやれたかな?」という感覚が大事なのです。
気にするべきは「日数」ではなく「仕組み」
習慣化に成功する人は、「何日続けたか」よりも、「どうやったら自然と続けられるか」に目を向けています。
たとえば、朝起きたらすぐストレッチをする、歯みがきのあとに英単語を見る、など行動の流れの中に取り入れているのです。
こうした仕組みがあると、「今日はやろうかな、やめようかな」と悩まずに済むので、続けやすくなります。
習慣になるまでの期間を乗り切るコツとその期間に私がやってること


- 意志が弱くても大丈夫!仕組み化テクニック3選
- 毎日じゃなくてもOK!最初は柔軟なルール設定をしよう
- 慣れてきたら自分に合ったやり方を見つけよう
- 私が習慣化のために実践していること
意志が弱くても大丈夫!仕組み化テクニック3選
「私は三日坊主だから無理…」と思っていませんか?
でも、習慣は意志の力ではなく、仕組みで続けるものです。
強い気持ちがなくても、毎日コツコツ続けられる方法はちゃんとあります。
ここでは、気合いに頼らず自然と行動が続けられる「仕組み化テクニック」を3つまとめました。


トリガー(きっかけ)を決める
習慣をつくるには、いますでにやっている行動とセットにするのが効果的です。
たとえば「歯みがきしながらスクワット」「朝のコーヒータイム中に日記を書く」といった感じで、すでにやっていることをトリガー(きっかけ)にすると忘れにくくなります。
これは「連結習慣(ハビット・スタッキング)」とも呼ばれる方法で、脳が「この動作の次はこれ」と覚えてくれるため、考えずに動けるようになります。
行動を思いきり小さくする
「今日はやる気が出ないな」と感じたときでも、やらなきゃ…と思うと重く感じてしまいます。
そこでおすすめなのが、習慣化したい行動をとにかく小さくすること。
たとえば「読書を10分」ではなく「本を1ページだけ開く」、「筋トレを10分」ではなく「とりあえず立ち上がる」だけでもOKです。
小さく始めれば心のハードルが下がり、自然と続けやすくなります。



習慣化したいことが不得意であればあるほど、行動は小さくするのをおすすめします。
記録をつけて達成感を育てる
人はできたという実感があると、もっと続けたくなります。
そこで役立つのが記録。
日めくりカレンダーに〇をつける、アプリでチェックする、ノートにメモするなど、形式は何でもかまいません。
記録が増えていくと、「せっかくここまで続いたから今日もやろう」と思えるようになり、自然とモチベーションが保てるようになります。
毎日じゃなくてもOK!最初は柔軟なルール設定をしよう
毎日やろうと決めたけど、できなかったからもうダメだ…。
こんな感じで挫折を経験した人も少なくないと思います。
でも、習慣は完璧に毎日やることがゴールではありません。
大切なのはムリせずに続ける工夫をすること。
ここでは、毎日やらなくても大丈夫と思える「柔軟なルールづくり」の考え方をまとめてみます。


毎日じゃなくても「週◯回」でも習慣になる
習慣化は毎日にやることにこだわる必要はありません。
たとえば「週に3回のウォーキング」でも、それが定着すれば立派な習慣。
習慣とは「やらなきゃ気持ち悪い」と思える状態のことなので、頻度より定着のしかたが大事なんです。
自分に合ったペースを決めよう
人にはそれぞれ生活のリズムがあります。
忙しい日もあれば、体調がすぐれない日もあるでしょう。
だからこそ、自分に合ったペースを最初から決めておくのが大事。
たとえば「平日はやらない」「日曜だけがんばる」でもOK。
大切なのは、「このやり方なら自分にもできそう」と感じられることです。
続けられたと思える工夫をしよう
続けられたという感覚が必ずモチベーションになります。
たとえ毎日できなくても、「ちゃんと今週も3回やれた」「先月よりサボる日が減った」と自分を認める仕組みをつくりましょう。
人は自分にやさしくできると、前向きな気持ちでまた始められます。
完璧より続いた自分に目を向けることが、習慣化にはとても大切です。
慣れてきたら自分に合ったやり方を見つけよう
これが正しい方法だという情報は世の中にたくさんあります。
でも、どんなに効果がある方法でも、それがあなたに合っていなければ続けるのは難しいですよね。
ひとりひとり個性もあるし、生活環境も違うし、まるっとひとくくりにはいきません。
習慣化に大切なのは、自分にピッタリ合うやり方を見つけること。
ここではその理由と見つけ方をまとめてみました。
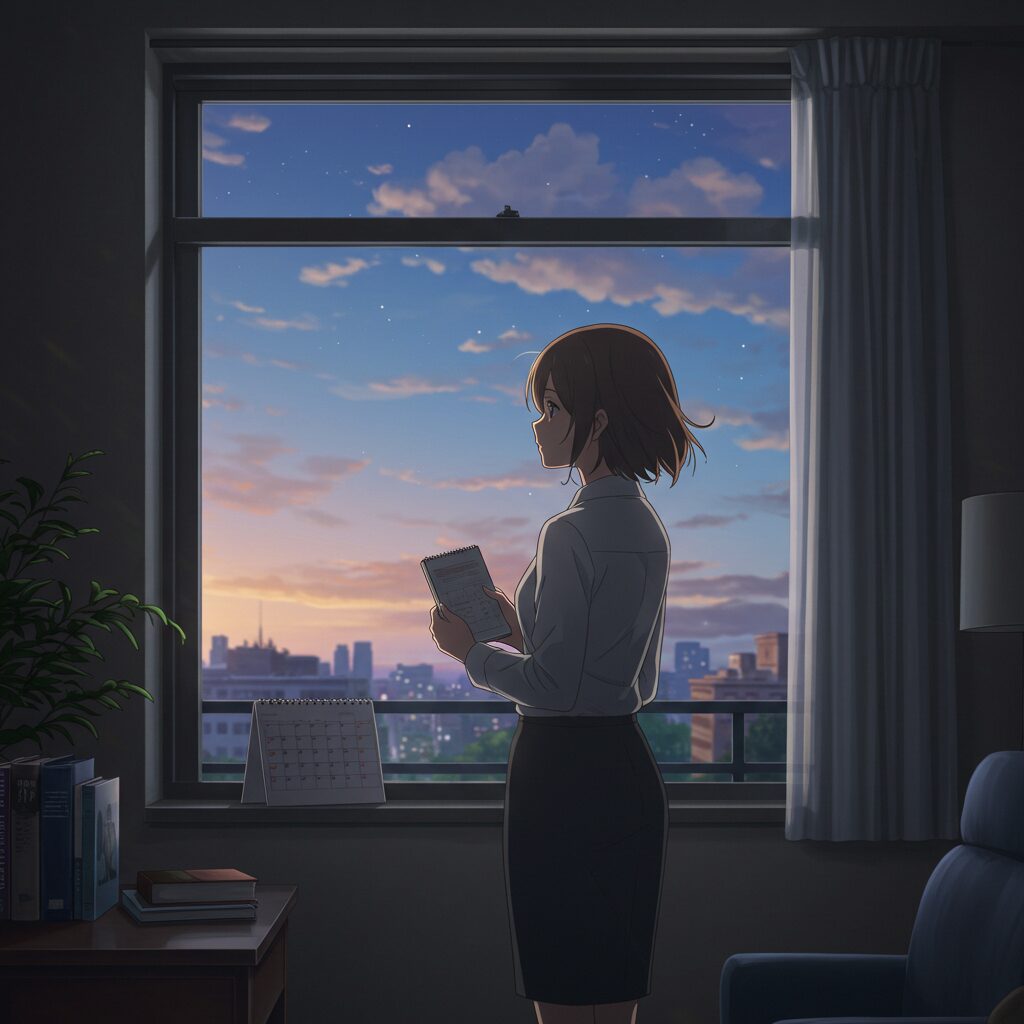
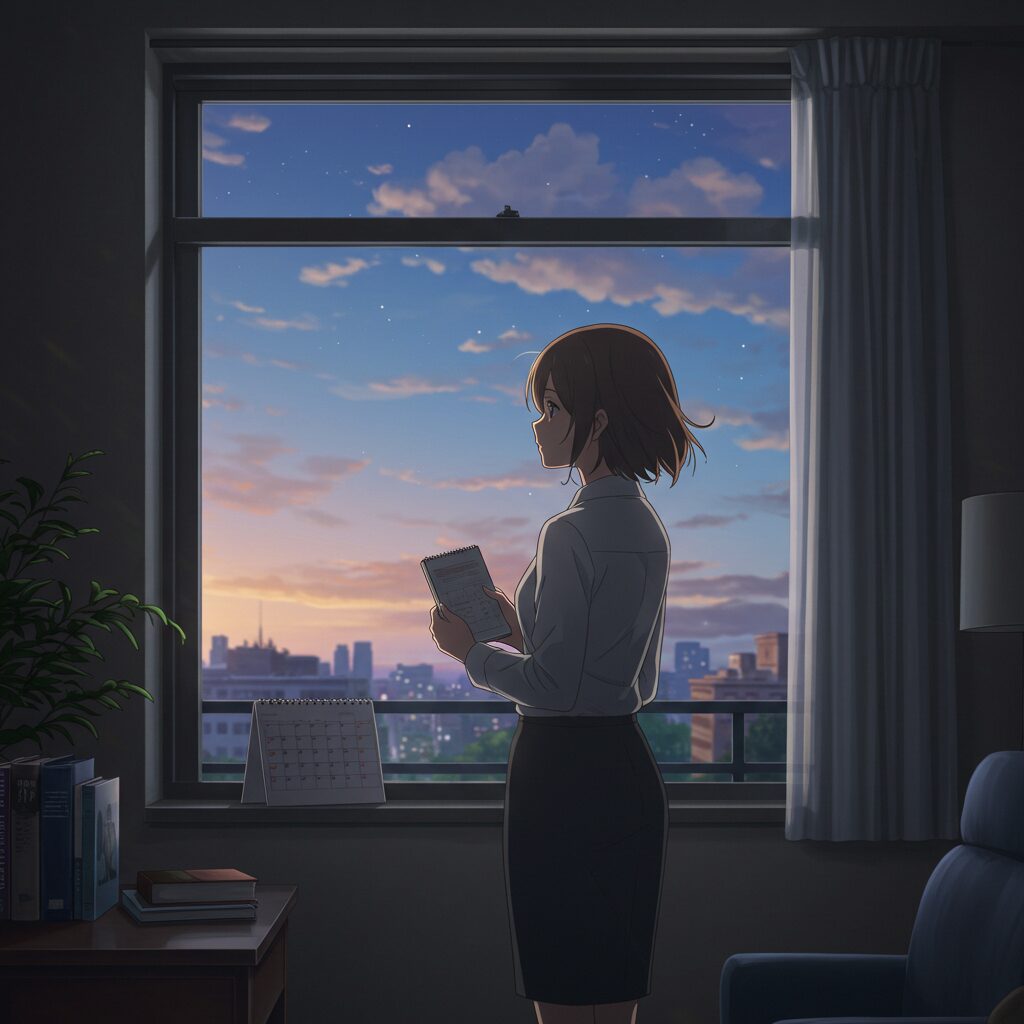
習慣は「誰かの正解」より「自分の心地よさ」で決まる
習慣は万人向けの正解ではなく、自分が心地よく続けられるかで決まります。
生活リズムや性格、価値観は人それぞれだからです。
誰かの成功例が、自分にそのまま当てはまるとは限りません。
たとえば「朝活が合わない人」にとって、無理やり早起きを習慣にしても長続きしないのは言わずもがなです。
朝が苦手であれば夜にやるとか自分が心地よいと思うやり方で進めていきましょう。



スタートは誰かのマネをしてもOKです!やっていくうちに改善点が見えるので、少しずつ自分色に変えながら進めていきましょう。
自分で選んだという感覚がやる気を生む
自分のペースや好みに合った方法を選ぶと、「これならできそう」「やってみたい」と感じやすくなります。
これは心理学でも「自己決定感」と呼ばれ、やる気を高める大事な要素。
人はやらされているより自分で決めた方ががんばれるんです。
たとえば、読書を習慣にしたいなら、「夜に10分だけ」「好きなジャンルから」など、自分でルールを作ると続きやすくなります。
自己決定感についての詳細はこちらのサイトを参照してください。
Psycho Psycho「自己決定感とは?その意味や自己決定感を高める方法について解説」
試してダメならやり方を変えればいい
うまくいかなかった時、「自分はダメだ…」と責める必要はまったくありません。
うまくいかない方法があったということは、次のステップへ進むヒントが見つかったということです。
習慣化は失敗しないことが目的ではなく、試してみて自分なりの方法に近づいていくことがゴールになります。
先ほど少し触れましたが、最初は誰かのマネからスタートしてもかまいません。
でも、そのやり方に少しずつ違和感を覚えたとき、そこでダメだと思うのではなく、別の方法に変えてみようと思えるかが大事なポイントです。
このように少しずつ改良を重ねながら続けていけば、気がついたときにはすでにそれが習慣化しているはずです。
私が習慣化のために実践していること
ハビットトラッカーで進捗の管理をしている
私は習慣化のツールとしてハビットトラッカーというものを利用しています。
以前書いた記事「100均の商品で「ハビットトラッカー」を上手に続ける方法」で触れたので、詳しくはこの記事を参照してください。
簡単に言うと、ハビットトラッカーとは習慣化したいことを記録するリストです。
習慣化したいことについて、できたらできたことを記録し、できなければできなかったことを記録していきます。
何でこんなことをしているかと言えば、成果を可視化するため。
先ほど少し触れましたが、記録しておくことでモチベーションを高めることができるのです。
記録しておけばこれまで積み上げてきたものの量が目で見てわかります。
実際にやってみるとわかるのですが、これがとても自信になるのです。



仕事も勉強も進捗状況は可視化できるようにしておくことをおすすめします!
目標を徐々にブラッシュアップさせる
私は習慣化したいことのひとつに「読書」を選んでいます。
習慣化するまでの期間を乗り切るためには目標のハードルをなるべく下げた方が都合が良いのは先ほど述べたとおりです。
これに従って、最初に立てた目標が「5分間読書」でした。
先ほど紹介した「100均の商品で「ハビットトラッカー」を上手に続ける方法」の中で、この習慣化をスタートさせたときのハビットトラッカーを公開しているので、よかった見てほしいのですが、たった5分の読書にもかかわらず、気が進まずにできない日(やりたくなくてやらなかった日)もあったんです。
それでも翌月になって慣れてきたのか毎日続くようになってきました。
そこで、その翌月から目標を「5分間読書」から「15分間読書」に切り替えて進めています。
実際問題、5分や15分の読書では読書量としてはそんなに大した量にはなっていません。
30分とか1時間とか言う時間で読み進めなければ、まともな読書とは言えないかもしれません。
でも、これまで読書らしい読書をしてこなかった私にとっては15分でも本を読めるようになったというのはちょっと誇らしさを感じてたりするんです。
これが小さな成功体験なんじゃないかと思っています。
今月15分読書に成功したら次は目標を30分にする予定です。
こんな感じでマイペースに習慣化を進めています。



最終的には1時間までいきたいです!
最後に習慣化するまでの期間についてまとめます
ここまでの内容を箇条書きでまとめます。
- 習慣が身につくまでにかかる期間は、平均で66日とされています。これは研究に基づいた数字ですが、あくまで参考値にすぎません。誰もが同じ日数で習慣化できるわけではないのです。
- 習慣が定着するスピードは、その人の性格やモチベーション、さらに行動の難易度によって大きく左右されます。たとえば、気軽にできることなら数週間で定着することもあれば、少し負担のあることは数ヶ月かかる場合もあります。
- 「何日続けたか」を気にするよりも、「どんな工夫をすれば自然と続けられるか」を考える方が、長く習慣を保ちやすくなります。○○日後に習慣化を目指すと言ったようにゴールを日数に設定すると、失敗したときに挫折しやすくなるからです。
- 続けるために必要なのは、気合や根性ではありません。自分の生活に合ったタイミングを決めたり、行動をとことん小さくしたり、記録して達成感を味わうなど、続けるための仕組みづくりが大切です。
- そして何より大切なのは、自分にとって心地よいやり方を見つけることです。最初は誰かのマネでもいいですが、自分が「これなら続けられそう」と思えるやり方こそが、本当の意味での正解なのです。
何かを習慣にしたいと考えたとき、いつまでに習慣化できるようにすると言った具合に、つい数字に頼りたくなってしまいます。
でも本当のゴールは、気づいたら自然にできていた、そんな習慣を育てること。
66日という平均日数はあっても、あなたのペースで、あなたらしい方法で続けることこそが何より大切です。
完璧じゃなくていいし、遠回りしてもかまいません。
少しずつ、自分にしっくりくる形を探していけば、それはいつしか、あなたの生活の中に当たり前のように溶け込んでいくはずです。
習慣化することをもっと気楽に楽しんでいきましょう。