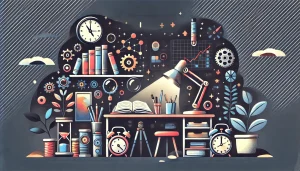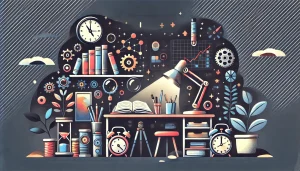「趣味はなんですか?」と聞かれて「勉強です」と答えたら、少し不思議な顔をされた経験はありませんか。
「休日に勉強はおかしくない?」「勉強が趣味なんて真面目だね」といった反応に、自分の感覚がずれているのかと不安になる方もいらっしゃるでしょう。
特に社会人になると、勉強から離れる人が多いのも事実です。
しかし、勉強しか趣味がないと感じていたとしてもそれは決してネガティブなことではありません。
むしろ、勉強が趣味の人は最強の存在にさえなりうるのです。
この記事では、なぜ趣味が勉強はおかしいと思われてしまうのか、その理由を解き明かしながら資格に向けた勉強の時間も含め、様々なジャンルの中から自分に合ったおすすめの勉強を趣味にする方法をまとめてみました。
- 趣味が勉強はおかしいと感じられてしまう社会的背景
- 勉強を趣味にすることで得られる多くのメリット
- 自分にぴったりの勉強ジャンルを見つけるヒント
- 無理なく楽しく勉強を趣味にするための具体的な方法
趣味が勉強はおかしいと感じる社会的背景
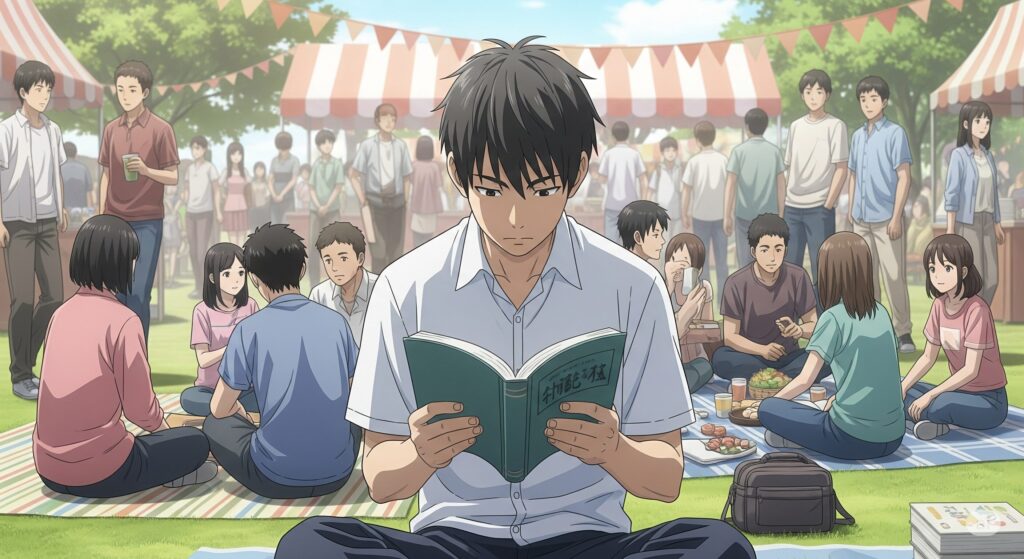
- 多くの社会人が抱く勉強への苦手意識
- 休日に勉強はおかしいという風潮の正体
- 勉強しか趣味がないことへの漠然とした不安
- 勉強と娯楽を対比で捉える一般的な価値観
多くの社会人が抱く勉強への苦手意識
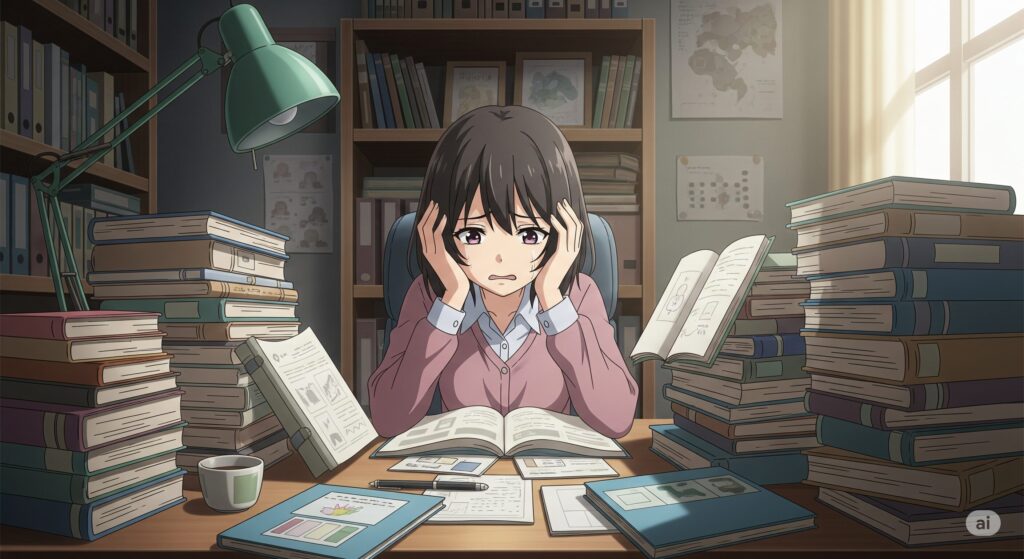
多くの社会人が勉強に対して、どこか苦手意識を持っているのは事実です。
実際に、総務省統計局の調査によると、日本に住んでいる10歳以上の人について、週全体平均による1日の生活時間を見たところ、学業以外の学習・自己啓発・訓練にかけた時間は、2016年では13分、2021年も同様に13分と、そもそも勉強が日常生活から遠い存在になっている現状があります。
この数字は総務省統計局令和3年社会生活基本調査の結果概要から引用したものです。
調査に関する詳細についてはこちらのサイトを参照してください。
総務省統計局 令和3年社会基本調査の結果
このため、勉強が趣味と聞くと、少し特殊なことのように感じてしまうのかもしれません。
その理由は、学生時代の経験に根差している場合がほとんどでしょう。
多くの人にとって、勉強は受験やテスト、成績といったプレッシャーと結びついています。
「勉強=辛いもの、義務的なもの」というイメージが、子供の頃から無意識のうちに刷り込まれてしまうのです。
例えば、興味のない科目を無理やり暗記させられたり、テストの点数だけで評価されたりした経験は、勉強そのものへの楽しさを見出す機会を奪ってしまいます。
このような経験から、大人になってからも自発的に勉強しようという意欲が湧きにくくなるのはある意味で自然なことだと言えます。
私も学生時代は、テストのための勉強が好きではありませんでした。
やらされてる感がとてもイヤだったこと思い出します。
でも、社会人になってから自分の興味のある分野を学ぶ楽しさを知り、勉強に対するイメージが180度変わりました。
このように、過去のネガティブな経験が自ら学ぶ楽しみを遠ざけている一因となっていることもあるのです。
休日に勉強はおかしいという風潮の正体
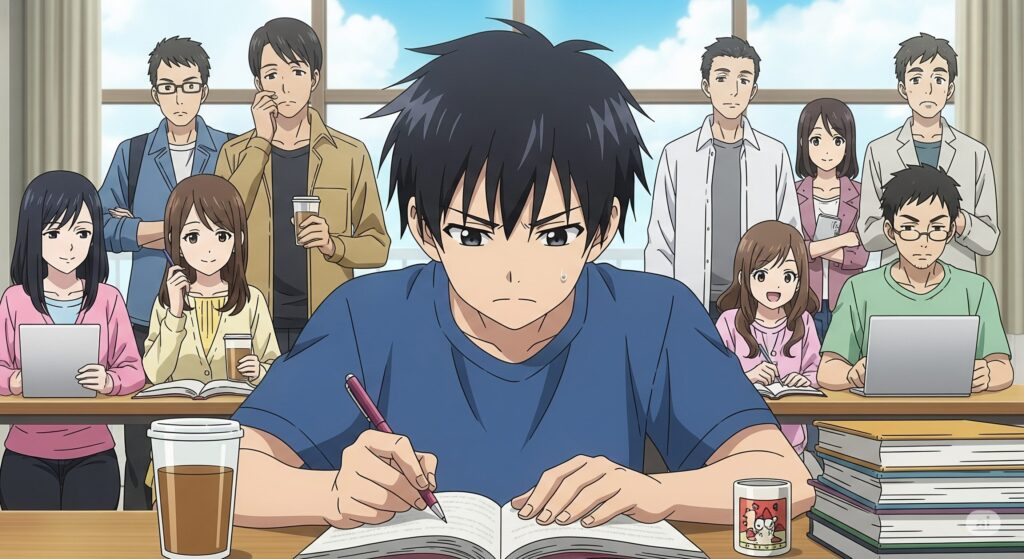
「休日にまで勉強するなんて、おかしいのでは?」という考え方が、世の中には少なからず存在します。
これは、「休日は心と体を休ませるための時間」という考え方が一般的であるためです。
多くの人にとって、休日は仕事の疲れを癒したり、趣味や娯楽に時間を使ったりするためのものです。
そのため、わざわざ休日にまで勉強という、どちらかといえば努力や苦労といったイメージのある活動をすることに違和感を覚えるのです。
また、日本では長時間労働が問題視される背景もあり、「休日に仕事に関連する勉強をすること=仕事の延長線上にある行為」と捉えられがちです。
オンとオフの切り替えができていない人、ワーカホリックな人というレッテルを貼られてしまうこともあります。
 かげとら
かげとら私は、仕事で楽をしたいからそのために休日に勉強しようと思うタイプです。
時には、同僚や友人との雑談でうっかり勉強の話をしてしまい、「意識高いね」と揶揄されたり距離を置かれたりすることがあるかもしれません。
しかし、趣味としての勉強は誰かに強制されるものではなく自らの知的好奇心を満たすための純粋な楽しみです。
リフレッシュの方法は人それぞれであり、勉強が最高のリフレッシュになる人もいるという多様な価値観がまだ浸透していないのが現状だと言えるでしょう。
勉強しか趣味がないことへの漠然とした不安
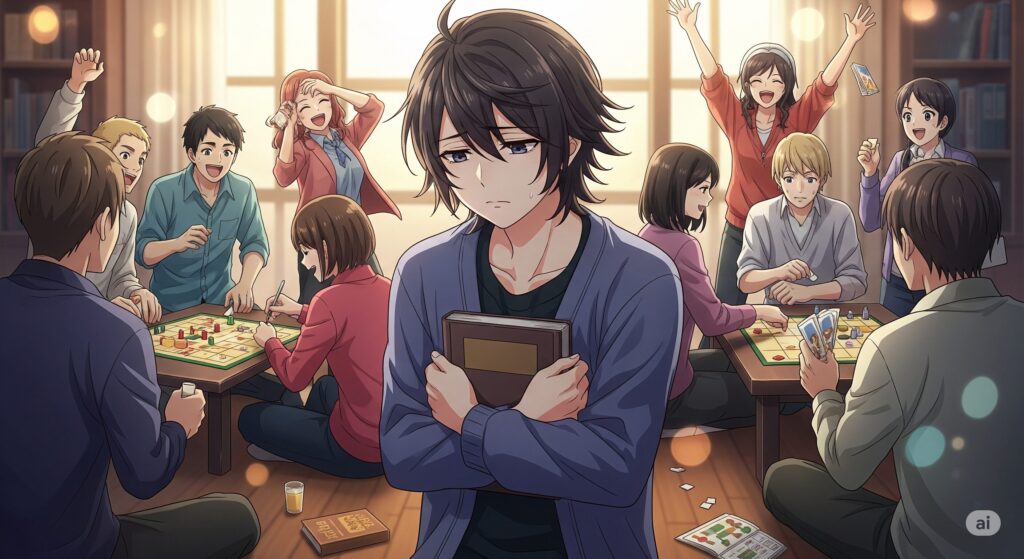
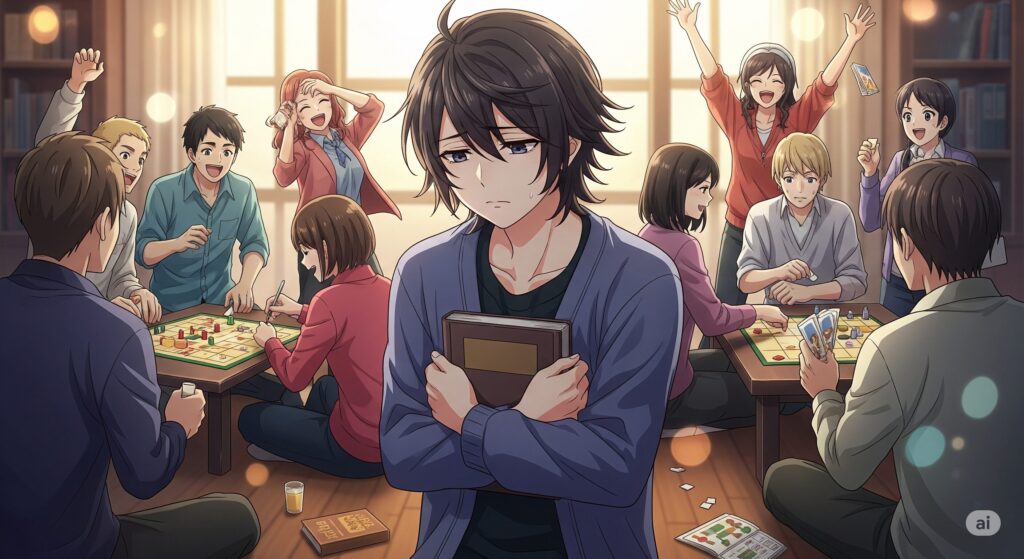
「自分には勉強しか趣味がない」と感じ、そのことに漠然とした不安を抱く方もいらっしゃいます。
この不安には、いくつかの心理が隠れていると考えられます。
一つは、「視野が狭くなってしまうのではないか」という懸念です。
勉強だけに没頭していると、他の活動、例えばスポーツや旅行、芸術鑑賞といった多様な経験から得られる学びや人との交流の機会を失ってしまうように感じられるかもしれません。
もう一つは、コミュニケーションへの不安です。
趣味の話題は、他人との雑談のきっかけになりやすいものです。
その中で趣味は勉強ですと答えることに抵抗があったり、相手と話が合わないのではないかと心配になったりするのです。
しかし、この不安は少し視点を変えることで解消できます。
勉強により一つの分野をとことん突き詰めることで得られる専門知識は、あなたの個性となり、あなたにとっての武器になるのです。
また、同じ分野の勉強を趣味にしている人と出会えれば、表層的な会話ではなく、非常に深く充実した人間関係を築くことも可能です。
言ってしまえば、あらゆる趣味は、突き詰めれば勉強の側面を持っています。
例えば、アニメが好きな人は声優や制作会社について詳しく調べますし、サッカーが好きな人は戦術や選手の歴史を学びます。
それらと本質的には何も変わらないのです。
勉強という言葉のイメージに過度に囚われる必要はありません。
勉強と娯楽を対比で捉える一般的な価値観


私たちの社会には、「勉強」と「娯楽」を完全な対極にあるものとして捉える価値観が根強くあります。
この二項対立の考え方が、「勉強が趣味はおかしい」という認識を生む大きな要因となっています。
| 勉強 | 娯楽 | |
|---|---|---|
| 目的 | 知識習得、自己投資、目標達成 | 楽しみ、リフレッシュ、ストレス解消 |
| プロセス | 努力、我慢、忍耐 | 快楽、興奮、癒し |
| 時間軸 | 将来のための投資 | その瞬間を楽しむ消費 |
このように、勉強は「未来のための苦労」、娯楽は「現在の楽しみ」として明確に区別されがちです。
このため、休日のような「現在の楽しみ」を追求すべき時間に、わざわざ「未来のための苦労」である勉強を選ぶことに対して、なぜ?という疑問が生まれるのです。
しかし、この境界線は本来もっと曖昧なものです。知らなかったことを知る喜び、できなかった問題が解けるようになる達成感は、娯楽にも通じる純粋な楽しさではないでしょうか。
実際、クイズ番組が人気を博したり、「知的好奇心」という言葉がポジティブに使われたりするように、「学ぶこと=楽しい」という感覚は多くの人が持っているはずです。
勉強という言葉が持つ、堅苦しいイメージが誤解を生んでいるだけなのかもしれません。
むしろ、消費するだけの娯楽とは異なり、自分の中に知識やスキルとして積み上がっていく勉強は、持続的な幸福感をもたらしてくれる、非常に生産的な活動だと言えるでしょう。
趣味が勉強はおかしいどころか最高の自己投資になる理由と始め方


- 勉強が趣味の人は最強だと言われる理由
- 知識習得がもたらす自己肯定感の高まり
- おすすめの勉強ジャンルで世界を広げよう
- 資格勉強も充実した趣味の時間になりうる
- 無理なく続く勉強を趣味にする方法とは
勉強が趣味の人は最強だと言われる理由


周囲からどう思われようと、勉強が趣味であることは人生を豊かにする上で非常に強力な武器となります。
むしろ、最強の趣味だとさえ言えるかもしれません。
その理由は、他の多くの趣味とは一線を画す数多くのメリットがあるためです。
以下にその理由を挙げてみます。
- 終わりなき探求
学ぶべきことは無限にあり、一生飽きることがありません。 - 低コスト
書籍代や教材費はかかりますが、他の趣味に比べて圧倒的にお金がかかりません。今ではネット上に無料の教材も豊富です。 - 場所を選ばない
本やPC、スマホさえあれば、自宅でもカフェでも通勤中でもどこでも趣味の時間に没頭できます。 - 資産になる
学んだ知識やスキルは、誰にも奪われることのないあなただけの一生の資産となります。 - 実益に繋がる
趣味で学んだことが、仕事の成果に直結したり、副業や転職に繋がったりと、金銭的なリターンを生む可能性があります。
例えば、ゲームに100時間費やしても、その経験が直接収入に繋がることは稀です。
しかし、プログラミングの勉強に100時間費やせば、それはキャリアの可能性を大きく広げる投資となりえます。
もちろん、全ての勉強が実益に繋がるわけではありません。
しかし、たとえ直接的なリターンがなくても、思考力や問題解決能力の向上、脳の老化防止といった、計り知れない恩恵を受けられるのです。
このように考えると、勉強が趣味の人は楽しみながら自分を成長させ続ける、まさに「最強」の存在だと言えるでしょう。
知識習得がもたらす自己肯定感の高まり


勉強を趣味にすることの大きなメリットの一つに、自己肯定感の向上が挙げられます。
自己肯定感とは、ありのままの自分を認め、価値ある存在として受け入れる感覚のことです。
勉強を通じて、この感覚を自然と育むことができます。
そのプロセスは非常にシンプルです。
- 知らなかったことを知る、分からなかったことが分かる。
- 難しい問題を解けるようになる、目標だった資格に合格する。
- 自分は成長しているという実感を得る。
- 達成感が自信となり、自分を肯定的に捉えられるようになる。
この「小さな成功体験」の積み重ねが、非常に重要です。
他者からの評価とは関係なく、自分自身の成長を実感できるため、揺るぎない自信が育まれていきます。
自信が持てると、物事をポジティブに捉えられるようになり、新しいことにも臆せずチャレンジできるようになります。
勉強で得た自信が、仕事や人間関係など、人生のあらゆる側面に良い影響を与えてくれるのです。
特に、大人になってからの勉強は、誰かに強制されるものではありません。
自分で決めたことを達成したときの爽快感は何物にも代えがたいものがあります。
自分の意志で学び、成長を実感する。
このサイクルこそが、健全な自己肯定感を育むための最高のトレーニングとなるのです。
おすすめの勉強ジャンルで世界を広げよう


「何か勉強してみたいけど何から始めればいいか分からない」という方のために、おすすめの勉強ジャンルを目的別にいくつかご紹介します。
自分の興味や目的に合わせて選ぶことで、より楽しく学習を続けることができます。
| 目的 | おすすめジャンル | 具体的な内容 | メリット |
|---|---|---|---|
| キャリアアップ・収入増 | 語学、プログラミング、Webマーケティング、会計・簿記 | TOEIC、英会話、Python、SEO、日商簿記 | 転職や副業に直結しやすく、実益に繋がりやすい。 |
| 生活を豊かにする | 金融リテラシー、法律、料理、健康・医学 | NISA・iDeCo、宅建、調理師免許、登録販売者 | 日々の生活に役立つ知識で、QOL(生活の質)が向上する。 |
| 知的好奇心を満たす | 歴史、哲学、芸術、天文学、特定の検定 | 世界史、西洋美術史、日本酒検定、漢字検定 | 純粋な「知る喜び」を追求でき、教養が深まる。 |
大切なのは、「少しでも興味が持てるか」という点です。たとえ人気のあるジャンルであっても、自分が全く興味を持てなければ長続きしません。
まずは書店や図書館に足を運び、様々なジャンルの本をパラパラとめくってみるのがおすすめです。
直感的に「面白そう!」と感じたものが、あなたにとって最高の勉強ジャンルになる可能性があります。
一つのジャンルを学ぶと、そこから関連する別のジャンルにも興味が広がり、学ぶこと自体がどんどん楽しくなっていく好循環が生まれます。
また、近年国も「リカレント教育(学び直し)」を推進しており、社会人が学びやすい環境が整ってきています。
文部科学省が運営する「マナパス」のようなポータルサイトでは、全国の大学や専門学校の講座情報を検索できるので、自分に合った学びを探すヒントになるでしょう。
ぜひ、あなたの世界を広げる一歩を踏み出してみてください。
資格勉強も充実した趣味の時間になりうる


資格勉強と聞くと、どうしても試験に合格するための苦しい作業というイメージが先行しがちです。
しかし、少し捉え方を変えるだけで、資格を取るための勉強は非常に知的で充実した趣味の時間となりえます。
ポイントは、合格だけを目的としないことです。
もちろん合格は大きな目標ですが、それ以上に「その分野の知識を体系的に学ぶプロセスそのものを楽しむ」という姿勢が大切になります。
例えば、ファイナンシャルプランナー(FP)の勉強を例に考えてみましょう。
- 単なる試験対策として捉える場合
「年金の計算式を暗記しなきゃ…」「相続の法律はややこしくて面倒だ…」 - 趣味として捉える場合
「なるほど、年金ってこういう仕組みで将来これくらい貰えるのか!」「自分の家の相続税はどうなるんだろう?」
後者のように、学んだ知識を自分の実生活と結びつけて考えることで、勉強は一気に自分ごととなり、面白みが増します。
歴史の資格であれば旅行先の見方が変わりますし、ワインの資格であればレストランでのワイン選びが格段に楽しくなるでしょう。
このように、資格取得に向けた勉強を趣味として楽しむにはコツがあります。
目的が「合格」だけになると途端に苦しくなるため、「知ること」自体に喜びを見出すことが重要です。
資格は、あなたの学びの成果を客観的に証明してくれる便利な指標です。
ゲームのクリアやトロフィー獲得のような感覚で楽しみながら挑戦してみてください。
無理なく続く勉強を趣味にする方法とは


勉強を趣味として長く楽しむためには、無理をせず習慣化するための工夫が必要です。
ここでは、誰でも今日から始められる、勉強を趣味にするための具体的な方法をいくつかご紹介します。
1. ハードルを極限まで下げる
最初から「毎日1時間勉強する!」と意気込むと、挫折しやすくなります。
まずは「毎日5分だけ参考書を開く」「通勤中に単語を一つだけ覚える」といった、絶対に達成できるレベルから始めましょう。
習慣化のコツは、やらないと気持ち悪いと感じるレベルまで、行動のハードルを下げることです。
2. 時間と場所を決める
「いつ、どこでやるか」をあらかじめ決めておくと、生活のルーティンに組み込みやすくなります。
例えば、「朝起きてすぐの15分間、ダイニングテーブルで」「寝る前の10分間、ベッドの中で」のように、具体的な行動計画を立てるのが効果的です。
3. 好きなことと組み合わせる
自分の好きなことと勉強を組み合わせるのも良い方法です。
- 好きな海外ドラマを字幕なしで見る(英語の勉強)
- 好きな音楽を聴きながらそのアーティストの歴史を調べる
- 好きなカフェで少しだけ勉強の時間を作る
このように、ポジティブな感情と結びつけることで勉強への抵抗感を減らすことができます。



習慣化についてはこちらの記事「習慣になるまでの期間ではなく習慣を作る仕組みを意識しよう」に詳細をまとめてあるので、こちらも読んでもらえると嬉しいです。
よくある質問と答え
最後に趣味が勉強はおかしいことではないことをまとめます
ここまでの内容を箇条書きでまとめます。
- 「趣味が勉強はおかしい」と感じるのは過去の経験や社会の風潮が原因
- 多くの社会人は勉強に苦手意識を持っているため共感されにくいだけ
- 休日に勉強することは自己投資であり決して無駄な時間ではない
- 勉強しか趣味がないと感じる必要はなく専門性は強みになる
- 勉強と娯楽の境界線は曖昧で学ぶこと自体に楽しみはある
- 勉強は低コストかつ場所を選ばずに始められる趣味
- 学んだ知識やスキルは誰にも奪われない一生の資産となる
- 趣味で得た知識がキャリアアップや収入増に繋がる可能性がある
- 小さな成功体験の積み重ねが自己肯定感を高めてくれる
- 無理なく続く勉強を趣味にするにはハードルを下げることが重要
- 自分の興味があるジャンルを選ぶことが継続の最大の秘訣
- 資格勉強もプロセスを楽しむことで充実した趣味になりうる
- 勉強は脳の老化予防など実用的なメリットも多い
- 知的好奇心を満たす行為は人生を豊かにする
- 周囲の目を気にせず自分の「好き」を追求することが大切