「仕事の効率を上げるために、もう紙の手帳はやめた」
近年、このように考える人が増えているそうです。
たしかに、社会人にはもう手帳はいらないのかもしれないと感じる場面は多いでしょう。
かつてビジネスパーソンの象徴だった分厚い手帳も、今ではシステム手帳は時代遅れで人によってはシステム手帳はダサいと感じることもあるようです。
お正月に満を持して使い始めた手帳も、結果的にほとんど使わないまま年末を迎えてしまったという経験を持つ方も多いかもしれません。
一方で、紙の手帳の脳科学的効用についての研究が進み、手書きの価値が見直されているのも事実です。
一度はデジタルに移行したものの、再び紙の手帳に戻したという声も少なくありません。
この記事では、紙の手帳をやめた人、そしてやめようか迷っている人、紙の手帳に戻ろうかと思っている人に向けて、その理由と背景を深掘りしていきます。
同時に、紙だからこその価値や、デジタルとアナログを融合させた新しい管理術についても多角的にまとめてみました。
あなたにとって最適な「答え」を見つける手助けができれば幸いです。
- 紙の手帳をやめる人の具体的な理由
- 紙の手帳ならではの脳科学的なメリット
- デジタルとアナログの最適な使い分け方
- 自分に合ったスケジュール管理術を見つけるヒント
なぜ紙の手帳をやめた人が増えているのか
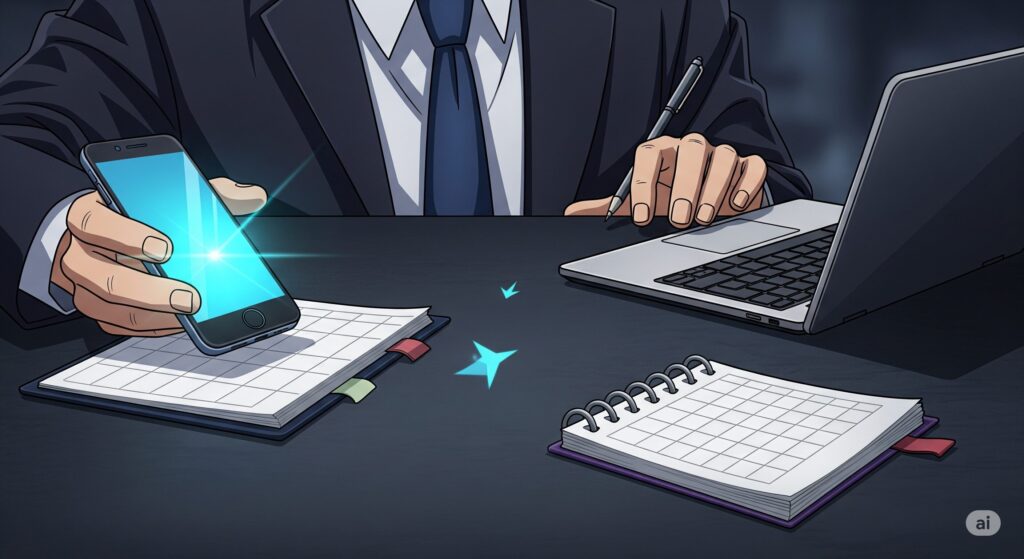
- 社会人には手帳がいらないという意見も
- システム手帳は時代遅れでダサいのか
- 結局ほとんどのページを使わないという現実
- 手帳をやめたらノートで十分だったという声もある
- 外国人は本当に手帳を使わないのか
社会人には手帳がいらないという意見も

現代の社会人にとって必ずしも紙の手帳は必須アイテムではなくなりました。
その最大の理由は、スマートフォンやPCで利用できるデジタルツールの台頭です。
例えば、GoogleカレンダーやTimeTreeといったスケジュール管理アプリは、多くのビジネスシーンで標準的に使われています。
これらのツールが持つメリットは紙の手帳にはない利便性を多数提供してくれる点にあります。
▼デジタルツールの主なメリット
- 共有機能
チームや家族と瞬時に予定を共有でき、認識の齟齬を防ぎます。 - リマインダー機能
設定した時間に通知が届くため、重要な予定を忘れる心配がありません。 - 連携機能
ZoomなどのWeb会議ツールと連携し、URLを予定に直接組み込めます。 - 修正の容易さ
予定の変更や削除が簡単で、手帳のように消し跡が残りません。
このように、特に他者との連携が重要な業務においてはデジタルツールの方が圧倒的に効率的です。
プライベートな予定管理においても、家族とのスケジュール調整が容易になるためデジタルを選ぶ人が増えています。
言ってしまえば、紙の手帳が担っていた役割の多くをスマートフォン一台で完結できるようになったのです。
これが、社会人には手帳がいらないという意見の大きな根拠となっています。
 かげとら
かげとら社会人の方で手帳がいらない派の人に向けて「手帳はいらない派の社会人へ!手帳が活躍する意外な瞬間とデジタル併用のすすめ」という記事も書いているのでこちらも読んでもらえると嬉しいです。
システム手帳は時代遅れでダサいのか


かつて、システム手帳は「できるビジネスパーソン」の象徴的なアイテムでした。
しかし、現在では「システム手帳は時代遅れ」「ダサい」という厳しい声が聞かれることも少なくありません。
なぜ、このようなイメージが定着してしまったのでしょうか。理由は主に以下の3つが考えられます。
1. 物理的な「重さ」と「大きさ」
システム手帳の多くは、重厚な革製のカバーと金属のリングが特徴です。
リフィルを追加すればするほど厚みと重さが増し、カバンの中でかなりのスペースを占有します。
現代のビジネススタイルがノートPCやタブレットを持ち歩くミニマルな方向へシフトする中で、物理的にかさばるシステム手帳は敬遠されがちです。
2. デザインの画一性と古さ
市場には多様なデザインの手帳が存在するものの、「システム手帳」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、黒や茶色の革製で、やや威圧感のあるデザインではないでしょうか。
この「いかにも」な見た目が、現代のカジュアルな服装や、自由な働き方にマッチしづらいと感じる人が増えています。
もっと言えば、「おじさん世代の持ち物」という固定観念が、若い世代から「ダサい」と見られる一因になっている可能性は否定できません。
3. コストパフォーマンスの問題
システム手帳は、本体カバーだけでなく毎年リフィルを買い替える必要があります。
質の良い革製カバーは1万円以上するものが多く、多機能なリフィルも決して安価ではありません。
スマートフォンアプリの多くが無料または低価格で高機能を提供していることを考えると、維持コストのかかるシステム手帳は、コストパフォーマンスの面で見劣りすると感じられても仕方がないでしょう。
もちろん、リフィルを自分好みにカスタマイズできる自由度の高さや、一つのものを長く愛用する満足感など、システム手帳ならではの魅力も存在します。
このように、時代の価値観やライフスタイルの変化が「時代遅れ」「ダサい」というイメージを助長している印象です。



私は古い人間なのかもしれませんが、今でもシステム手帳がカッコいいと思っているタイプです。でも自分の場合、実用を考えるとちょっとゴツいんですよね・・・。
結局ほとんどのページを使わないという現実
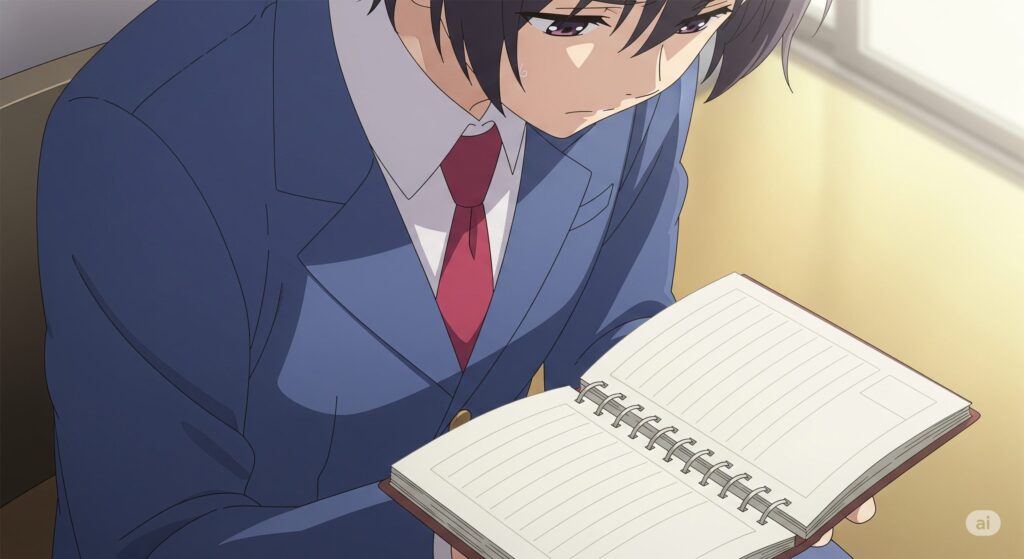
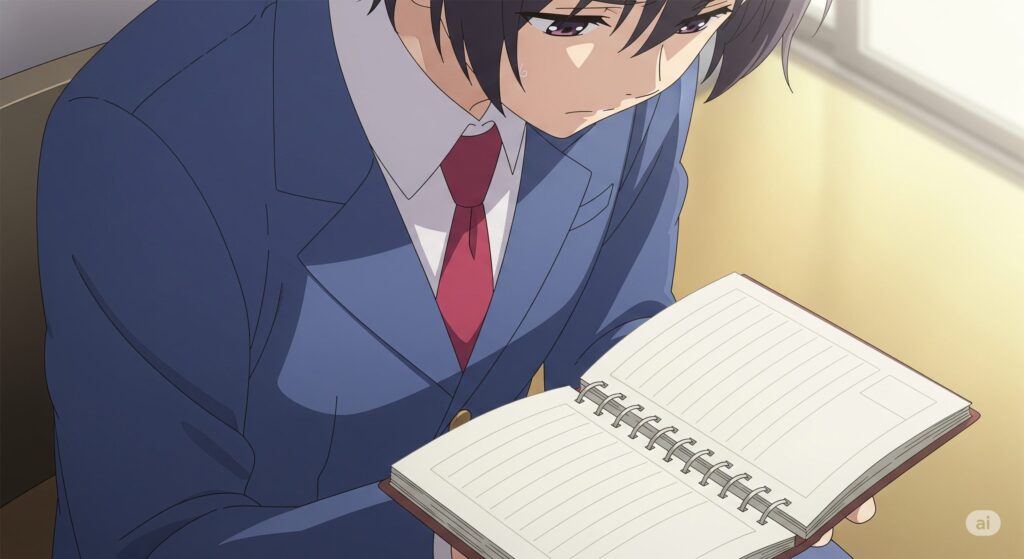
手帳選びで多くの人が経験する失敗の一つに、「意気込んで高機能な手帳を買ったものの、結局ほとんどのページを使わなかった」というものがあります。
特に、1日1ページタイプの「ほぼ日手帳」や、時間軸が詳細なバーチカルタイプの手帳で起こりがちな現象です。
年の初めには「日記を書こう」「日々の記録をつけよう」と目標を立てるものの、数週間も経つと書くことがなくなり、真っ白なページが続いてしまうのです。
空白のページが続くと、それがプレッシャーになって、ますます手帳を開くのが億劫になる…という負のループに陥りがちですよね。
この罪悪感が、手帳を持つこと自体のハードルを上げてしまっています。
この問題の根底には、理想の自分と現実の生活とのギャップがあります。
手帳のフォーマットに自分の生活を合わせようとすることで、無理が生じてしまうのです。
毎日びっしりと書き込むような生活を送っていないにもかかわらず、広大なスペースを持つ手帳を選んでしまう。
その結果、手帳を「使いこなせない自分」を責めることになり、手帳そのものから離れていく、というパターンは非常に多いと言えるでしょう。



手帳を買っても結局使わない人に向けて「手帳を買っても結局使わないで終わるのはなぜ?続ける人の活用術とは」という記事もあるのでこちらも読んでもらえると嬉しいです。
手帳をやめたらノートで十分だったという声もある
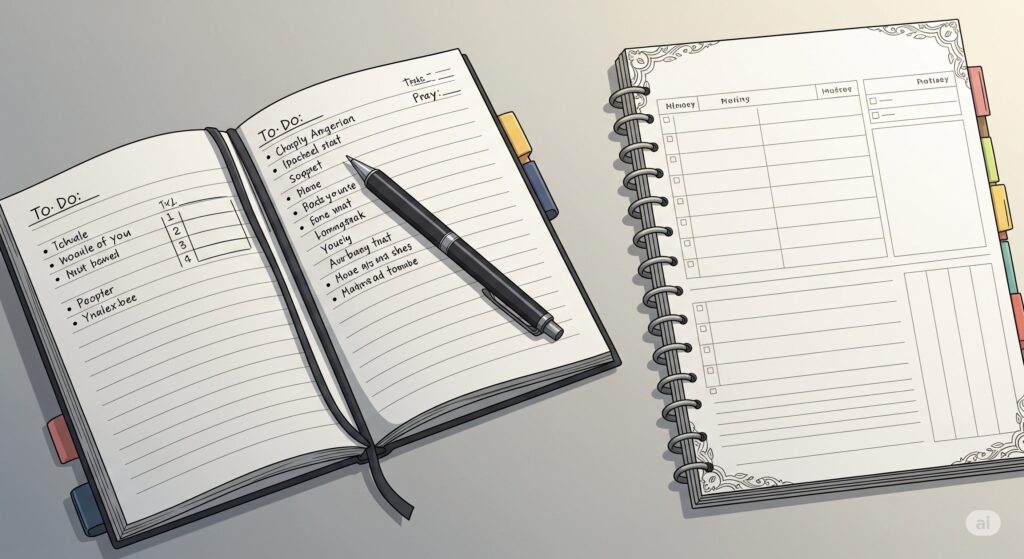
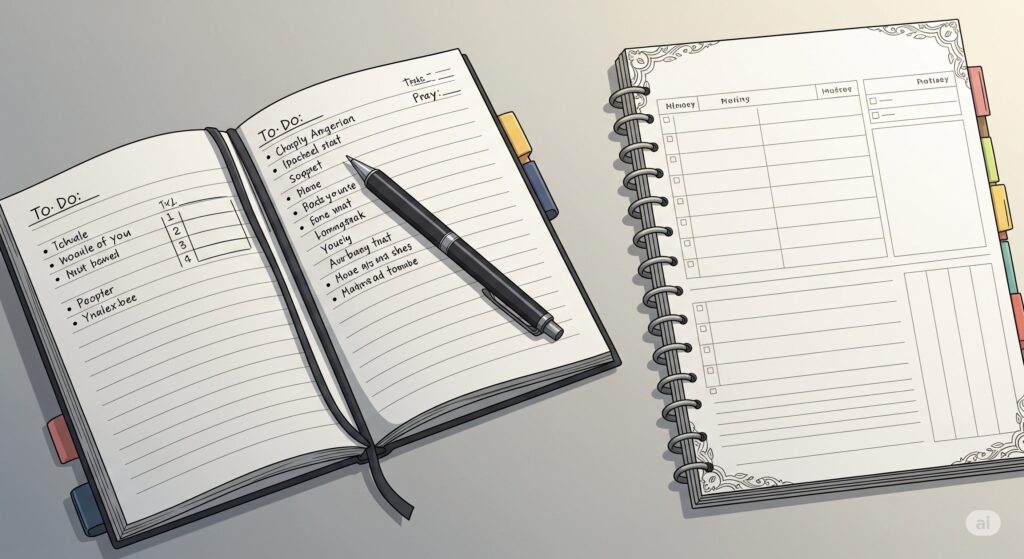
既製品の手帳が持つフォーマットの制約から解放される手段として、近年注目を集めているのが「ノート」を使ったスケジュール管理です。
特に「バレットジャーナル」という手法は、多くの人に受け入れられています。
バレットジャーナルとは、簡単に言えば「箇条書き」をベースにしたノート術です。
市販の好きなノートに自分で決めたルールでタスクや予定、メモなどを書き出していきます。
日付や形式に縛られないため書くことがない日はページを空ける必要がなく、自分のペースで続けられるのが最大の魅力です。
▼ノートで管理するメリット
- 自由度が高い
カレンダー、ToDoリスト、日記など、必要な要素だけを自分で構成できます。 - コストが低い
数百円のノートから始められ、高価な手帳を買う必要がありません。 - 継続しやすい
白紙のページに対するプレッシャーがなく、挫折しにくいです。 - 一元管理できる
スケジュールもアイデアも、全ての情報を1冊のノートに集約可能です。
例えば、コクヨや無印良品の方眼ノートやドット方眼ノートは、線を引いたり図を書いたりしやすいためバレットジャーナル初心者にも人気があります。
このように、高価な手帳を使わなくてもシンプルなノートとペンさえあれば、スケジュール管理は十分に可能なのです。
「手帳をやめたら、むしろ快適になった」という声が多いのも頷けます。
外国人は本当に手帳を使わないのか


「海外のビジネスパーソンは日本人ほど手帳を使っていない」という話を聞いたことはないでしょうか。
これは、ある程度事実と言えます。
もちろん海外にも「ファイロファックス」のような有名な手帳ブランドは存在します。
しかし、日本の書店のように年末になると多種多様な手帳が並ぶ光景はあまり一般的ではありません。
この背景には仕事の進め方や文化の違いが関係していると考えられます。
例えば、日本のビジネス文化では依頼されたタスクを一度「To-Doリスト」に書き留め、後で処理するという進め方が一般的です。
一方、欧米などでは電話や依頼があれば可能な限りその場で対応し、仕事を完結させようとする傾向があります。
「リストに書く」というワンクッションを挟まず、タスクを即時処理することで手帳にメモする必要性そのものを減らしているのです。
不在の相手に電話をかける際も「改めてこちらから掛け直します」ではなく、「私に電話をくれるよう伝えてください」と、タスクを相手に渡す文化もあります。
これも、自分の手帳に「再電話」と書く必要をなくす工夫の一つですね。
このように言うと、日本的な働き方が非効率に聞こえるかもしれませんが、相手への配慮を重んじる素晴らしい文化でもあります。
ただ、「手帳に書き留める」という行為が日本のビジネス慣習と密接に結びついているのは事実です。
逆に言えば、仕事の進め方を変えることで、手帳への依存度を下げられる可能性も示唆しています。
紙の手帳をやめたからこそ見える本当の価値


- 紙の手帳がもたらす脳科学的な効用
- デジタル移行後に紙の手帳へ戻した人々
- 「超整理手帳」をやめた人は次に何を選んだのか
紙の手帳がもたらす脳科学的な効用
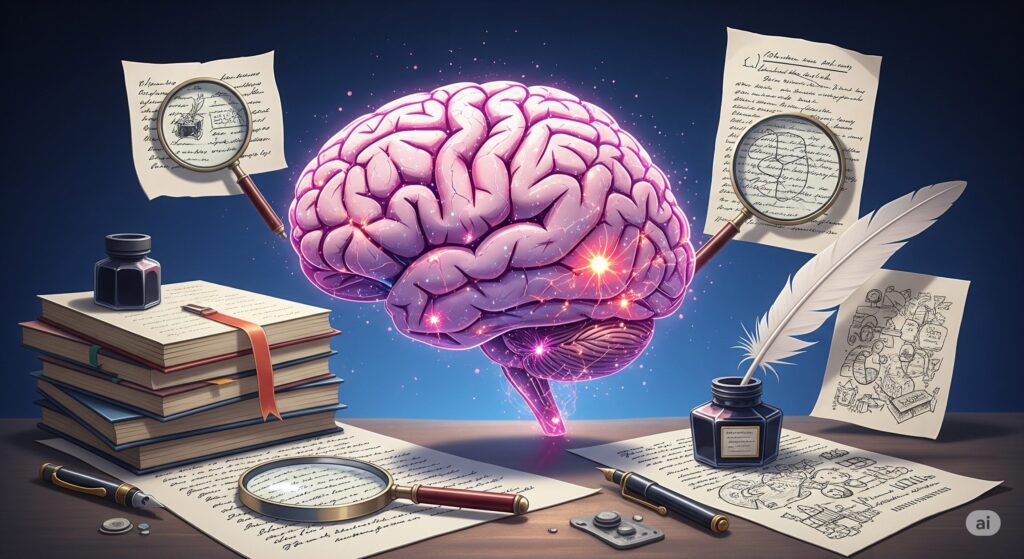
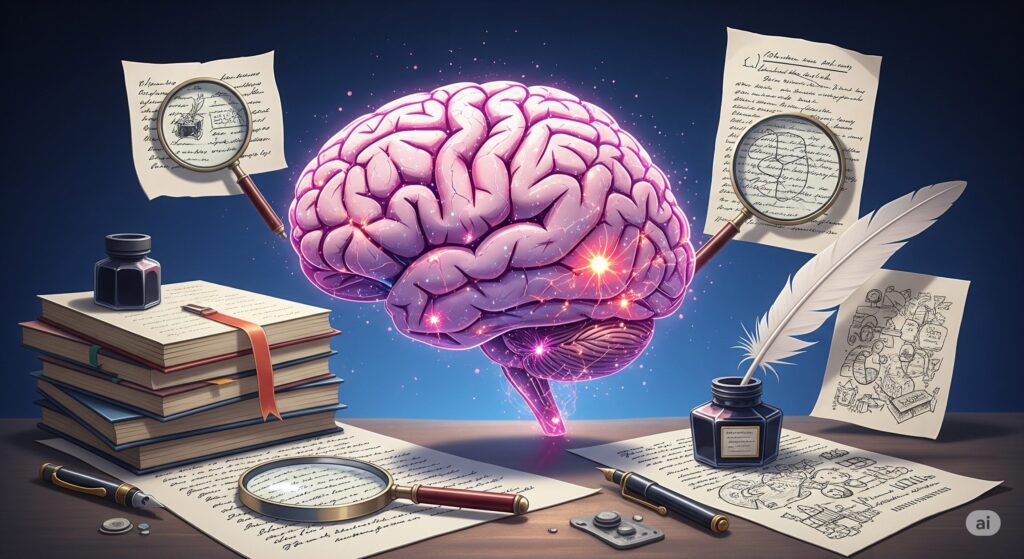
デジタルツールの利便性が高まる一方で、近年、紙とペンで「手書き」することの価値が科学的に見直されています。
特に、東京大学の研究グループが発表した研究結果は多くのメディアで取り上げられました。
この研究では、紙の手帳、タブレット、スマートフォンの3つのグループに分かれてスケジュールを記憶してもらい、その後の脳活動を比較しました。
その結果、紙の手帳を使ったグループは、他のグループに比べて、記憶を思い出す際に脳の「海馬」や言語に関する領域がより活発に活動したことが分かったのです。(参照:東京大学 プレスリリース)
海馬は記憶を司る重要な領域です。
つまり、紙の手帳に手で書く行為は単なる記録以上に記憶の定着を強く促す効果があることを示唆しています。
| メディア | 特徴 | 脳への影響 |
|---|---|---|
| 紙の手帳 | 紙の質感、書いた場所の位置、ペンの感触など、五感を使う情報が豊富。 | 空間的な手がかりが多く、記憶を司る海馬が活性化しやすい。結果として、記憶に残りやすい。 |
| デジタル機器 | スクロールすると表示位置が変わり、物理的な手がかりが乏しい。入力方法が画一的。 | 紙媒体に比べ、記憶想起時の脳活動が低い傾向にある。手軽だが、記憶の定着度は劣る可能性がある。 |
この研究の興味深い点は、「手書き」の効果だけでなく、「紙」という媒体そのものの重要性を指摘していることです。
紙の上のどこに何を書いたかという空間的な情報が、記憶を引き出すための強力なフックになると考えられています。
創造的なアイデアを出す際にもこの「記憶の引き出しやすさ」が有利に働く可能性があります。
デジタル移行後に紙の手帳へ戻した人々


一度はデジタルツールに完全移行したものの、再び紙の手帳を使い始める「出戻り組」も少なくありません。
彼らが紙の手帳に戻る理由は何なのでしょうか。
主な理由として、デジタルツールの限界やデメリットが挙げられます。
▼デジタルツールの主なデメリット
- 一覧性の低さ
月間や年間の予定を俯瞰(ふかん)しづらい。スマートフォンの小さな画面では特に顕著。 - 思考の妨げ
スケジュールを確認しようとスマホを開いたのに、通知やSNSに気を取られてしまう。 - バッテリー依存
充電が切れたら何も確認できなくなるという不安がつきまとう。 - 手書きの自由度の欠如
図やイラストを描いたり、思考を自由に書き出したりするには不向きな場合が多い。
特に、「思考を整理する場」として、紙の手帳の価値を再認識する人が多いようです。
デジタルツールが「タスク管理」に特化しているのに対し、紙の手帳は予定もアイデアも悩みもすべてを受け止めてくれる余白があります。
キーボードで入力するのではなく、自分の手で文字や図を書くプロセスそのものが、頭の中を整理し新しい発想を生むきっかけになるのです。
また、過去の手帳を物質的に保管できる点も魅力の一つです。
数年前に自分が何を考えどんな毎日を送っていたのかを、手触りやインクの濃淡とともに振り返ることができる。
これは、クラウド上にデータとして残るのとは全く異なるアナログならではの情緒的な価値と言えるでしょう。
「超整理手帳」をやめた人は次に何を選んだのか
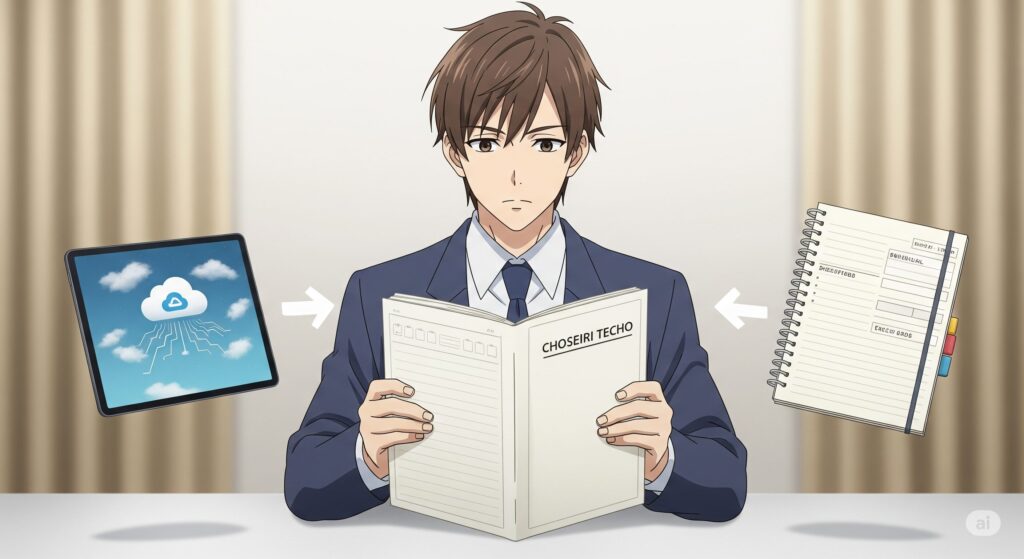
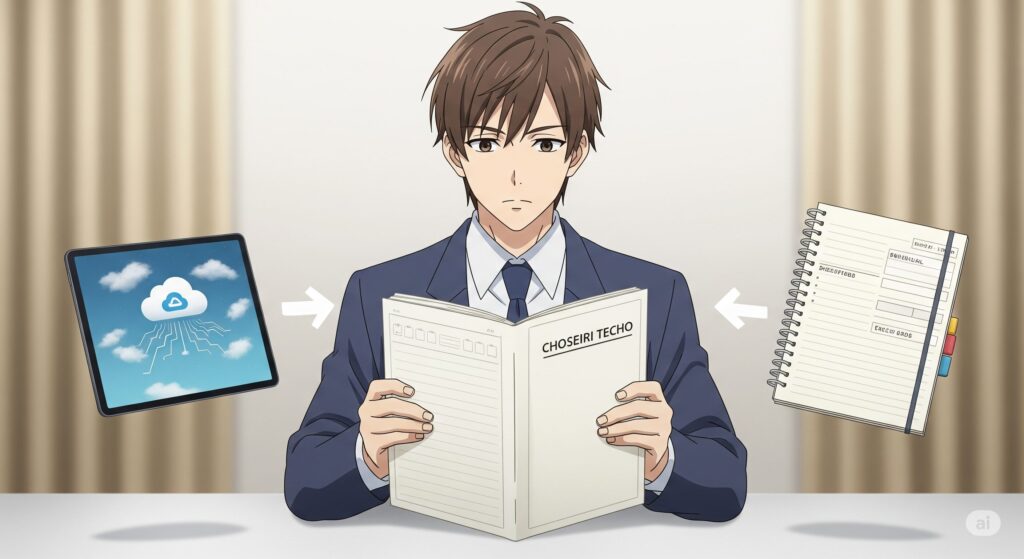
経済学者の野口悠紀雄氏が考案した「超整理手帳」は、そのユニークなコンセプトで一時代を築きました。
最大の特徴は、A4用紙を四つ折りにしたサイズ感と、すべての情報をA4サイズで一元管理するという思想です。
会議資料もメモもチケットも、すべてA4サイズに集約し、時系列で並べて手帳に挟み込む。
この方法は、紙媒体が情報管理の中心だった時代において非常に画期的なものでした。
しかし、時代はペーパーレス化へと大きく舵を切りました。
多くの資料はデータで共有されてチケット等も電子化が一般的になりつつあります。
こうなると、超整理手帳の根幹であった「A4書類の一元管理」というメリットが活かしにくくなってしまったのです。
では、超整理手帳をやめた人々は次に何を選んだのでしょうか。
その選択は大きく2つのパターンに分かれます。
- デジタルへの完全移行派
情報のデジタル化という時代の流れに乗り、EvernoteやNotionといったクラウドサービスに情報を集約するパターンです。「A4での一元管理」という思想を、デジタル上で実現しようとする人々と言えます。 - 別のノート術への移行派
バレットジャーナルやA5サイズのシステム手帳など、より柔軟性の高いアナログ手法に移行するパターンです。「情報を一元管理したい」という思想は維持しつつ、A4というフォーマットの縛りから解放されたい、というニーズを持つ人々です。
超整理手帳の事例は、どんなに優れたツールであっても、時代の変化や個人のワークスタイルの変化によって、その役割を終えることがあるということを示しています。
重要なのは一つの方法に固執するのではなく、常に自分にとっての「最適解」を探し続ける姿勢なのかもしれません。
紙の手帳をやめたあなたへ
最後に本記事の要点をまとめます。
- 紙の手帳をやめる最大の理由はデジタルツールの普及にある
- スケジュール共有やリマインダー機能はデジタルが圧倒的に便利
- システム手帳は重さやデザインから時代遅れと感じられることがある
- 高機能な手帳を買っても使わないまま白紙のページが増えがち
- バレットジャーナルなどノート術の登場で手帳の代替が可能になった
- 海外では日本ほど手帳文化が根付いていない背景に仕事の進め方の違いがある
- 一方で紙の手帳に手書きすることは脳科学的に記憶の定着を促す
- 紙の上のどこに書いたかという空間情報が記憶のフックになる
- デジタルツールの一覧性の低さや不自由さから紙に戻る人もいる
- 手書きのプロセスは思考の整理やアイデア出しに役立つ
- 過去の手帳が物質として残り自分の足跡を振り返れる価値がある
- 超整理手帳のように優れたツールも時代の変化で役割を終えることがある
- 大切なのは一つの方法に固執せず自分に合った方法を探し続けること
- 紙のメリットを他の方法で得られるなら無理に使う必要はない
この記事では、紙の手帳をやめるという選択の背景にあるデジタルツールの利便性やライフスタイルの変化に触れる一方で、手書きがもたらす脳科学的な効用や思考を深める力といった紙ならではの価値についても掘り下げてきました。
デジタルがもたらす圧倒的な効率性と、アナログな手帳が育む思考の深さ。
どちらにも、それぞれの場面で輝く代えがたい魅力があります。
大切なのは流行や「こうあるべき」という固定観念に縛られることなく、ご自身の仕事や生活のスタイルに本当にフィットする方法をご自身の意思で選び取ることです。
手帳をやめる、続ける、戻る、あるいはノートやアプリと併用する。
どんな選択もあなたにとっての正解と言えるでしょう。
この記事が、その最適解を見つけ出し日々の暮らしをより豊かにするためのコンパスとなればこれほど嬉しいことはありません。
