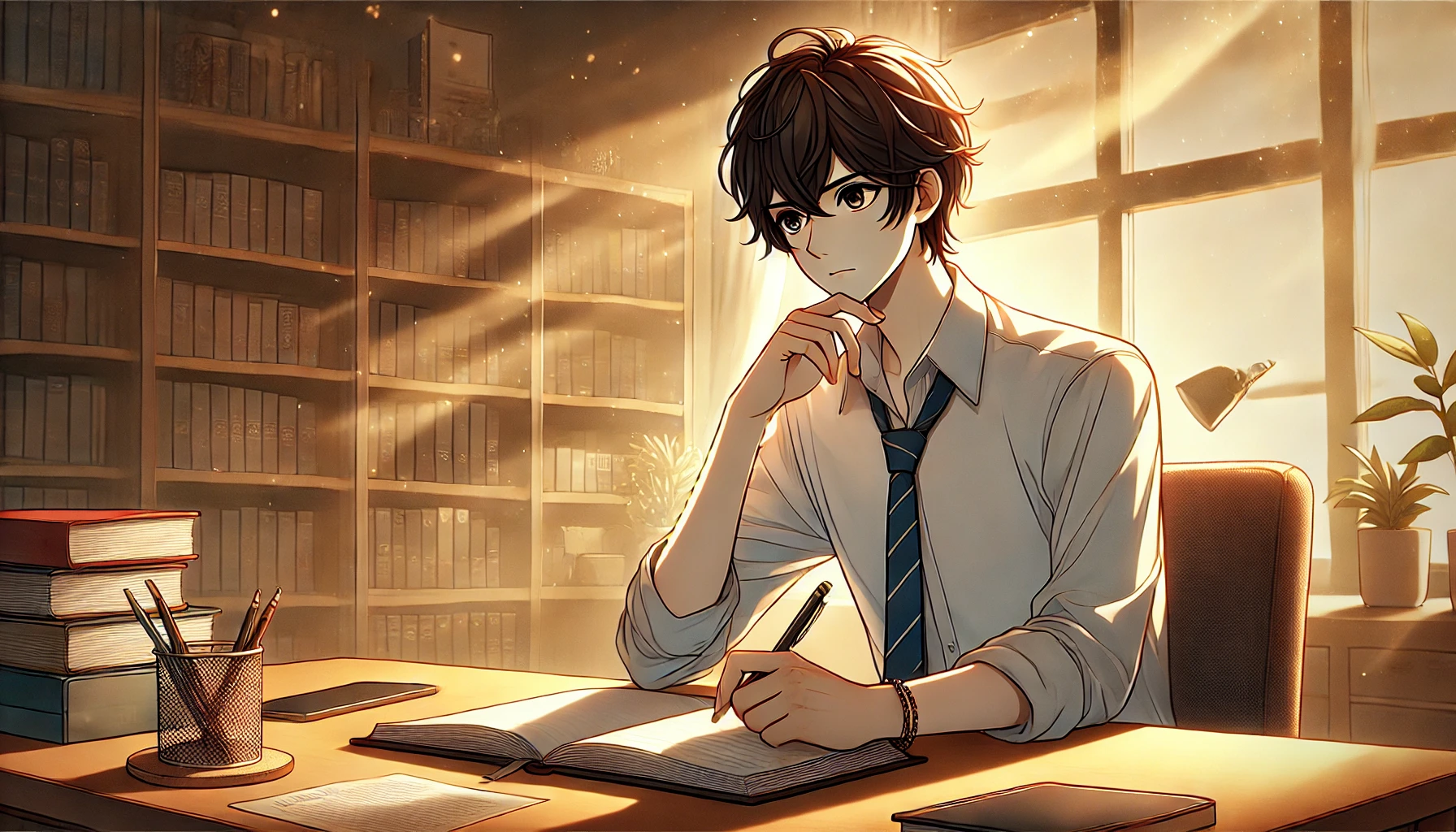この記事に目を留めた方の多くは、メモの取り方や活用方法に迷いを感じているのではないでしょうか。
たとえば、せっかくノートに書いても「効果が感じられない」「どう書けばいいのかわからない」といった疑問や不安を抱えているケースも少なくありません。
この記事では、そうした悩みを抱える方に向けて、「メモの魔力」という本を紹介しながら、メモすることを意味あるものに変えるためのノートの書き方や使い方をまとめてみました。
特に、つまずきやすい抽象化のコツや、続けやすくするためのテンプレート、自己分析に活かせる具体的な方法、ノートのサイズ選びのポイント、そして実感しやすいメリットなどを紹介しています。
小さな工夫で、メモは単なる記録から「自分を変える道具」へと変わるのです。
読み進める中で、あなただけの使えるメモ術が見つかったら幸いです。
- メモの魔力が意味ないと感じる原因と対処法
- 抽象化や転用を使ったノートの具体的な書き方
- 自己分析に役立つテンプレートと活用方法
- 続けやすいノートのサイズや使い方の工夫
ノートへの書き方次第でメモの魔力は意味ないものになるかも
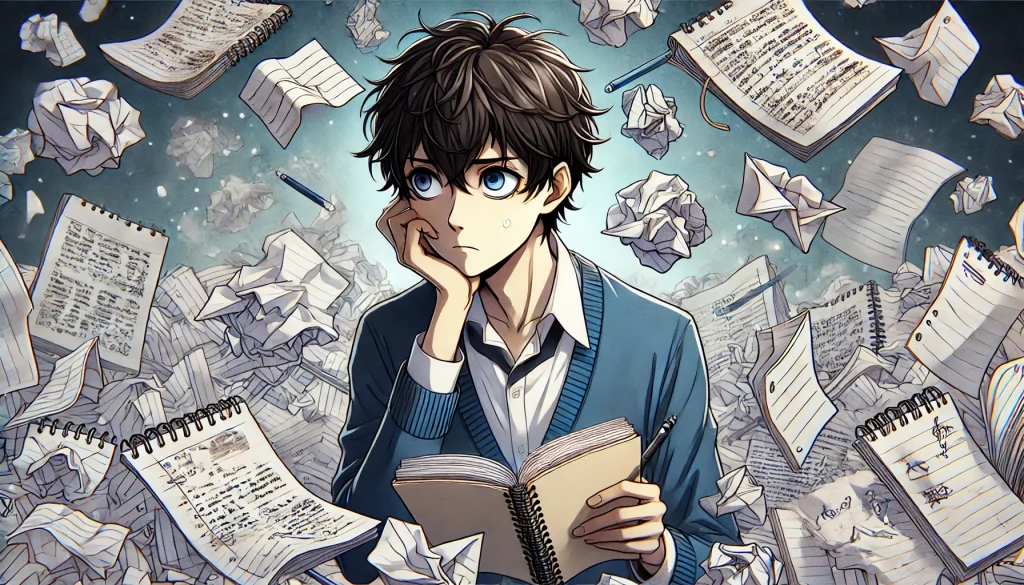
- メモの魔力とは?
- メモに意味ないと感じる理由
- 難しいと感じる人の共通点と原因
- 初心者でも迷わないメモを取るやり方
- 抽象化が難しいと感じる原因とは
- 自己分析に役立つテンプレート紹介
メモの魔力とは?
「メモの魔力」は、SHOWROOM代表の前田裕二さんが書いたビジネス書で、ただのメモを「自分の人生を変える道具」にまで高めようという内容です。
メモと聞くと多くの人が「話を記録するためのもの」と考えがちですが、この本ではそれ以上の役割を持っているとされています。
具体的には、見たこと・聞いたことを記録するだけでなく、それを自分の言葉で深く考え、行動につなげるという点が特徴です。
たとえば、「大阪ではチラシにアメをつけると反応が良かった」という事実を知ったとします。
ただ記録するだけで終わらず、「大阪の人は目に見えるメリットに反応しやすいのかもしれない」と考える。

そして最後に「自分の仕事でも、わかりやすいメリットを提示してみよう」と実際に活かす。
この一連の流れが「ファクト→抽象化→転用」というメモ術の核です。
このように、ただのメモを「思考を深めるための道具」に変える点が「メモの魔力」と呼ばれる所以です。
ただし注意点もあります。
慣れないうちは、抽象化や転用が難しく感じるかもしれません。
また、すべての出来事に意味を見いだそうとすると少し疲れてしまうこともあるはず。
最初は完璧を目指さず、まずは「気になったことを書く」だけでも十分です。
この本の目的は、メモを使って自分の感性を磨いたり、考える力を育てたりすることにあります。
特別なスキルがなくても、少しずつ実践していけば、誰でも「知的なメモ」ができるようになります。
メモに意味ないと感じる理由
「メモって、意味あるのかな?」と感じたことがある人は意外と多いかもしれません。
その理由のひとつに、「メモをとっても見返さないから」という声があります。
メモをとったときには「いいこと書けた」と思っても、あとで見返すことがなければ、それはただの書きっぱなしになってしまいます。
使わないメモは、当然役に立っている実感もわきにくいです。
また、「メモの内容がよくわからない」というケースもあります。
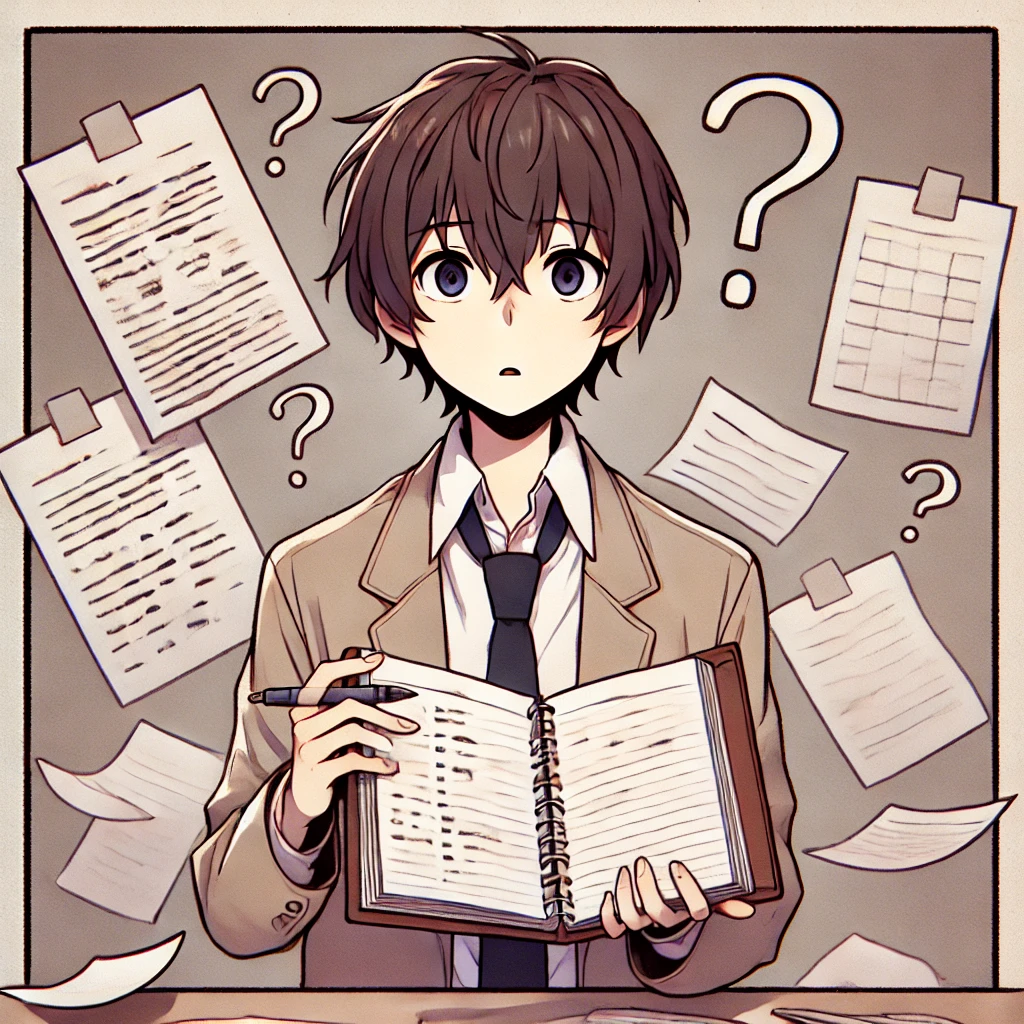
話を聞きながら急いで書くと、あとから見ても文字が汚かったり、何のことだったか思い出せなかったりします。
こうした経験があると、「書いてもムダだったな」と感じやすくなるのです。
さらに、完璧なメモをとらなければいけないと思い込んで、続けるのがつらくなることもあります。
とくに几帳面な人ほど、「ちゃんとまとめなきゃ」と考えてしまいがちです。
しかし、その気持ちがプレッシャーとなって、「やっぱりメモは自分に向いてない」と感じてしまう原因になるのです。
こうした気持ちが積み重なると、「メモは意味ない」「結局続かない」と思ってしまうようになります。
でも、実はメモに正解はありません。
自分が使いやすい形で、自由に書いていいものなのです。
完璧を目指すよりも、まずは自分にとっての「使いやすいメモ」を見つけてみるのが第一歩です。
難しいと感じる人の共通点と原因
「メモの魔力を実践しようと思ったけど、なんだか難しくて続かない……」そんな声もよく耳にします。
うまくいかないと感じる人には、いくつかの共通した特徴があります。
まず多いのが、「最初から正しくやろうとしすぎてしまう人」です。
たとえば、メモのルールや書き方にこだわりすぎて、「これは正しいメモになっているのかな?」と不安になってしまうと、手が止まってしまいます。
結果として「自分には難しい」と感じてしまうのです。
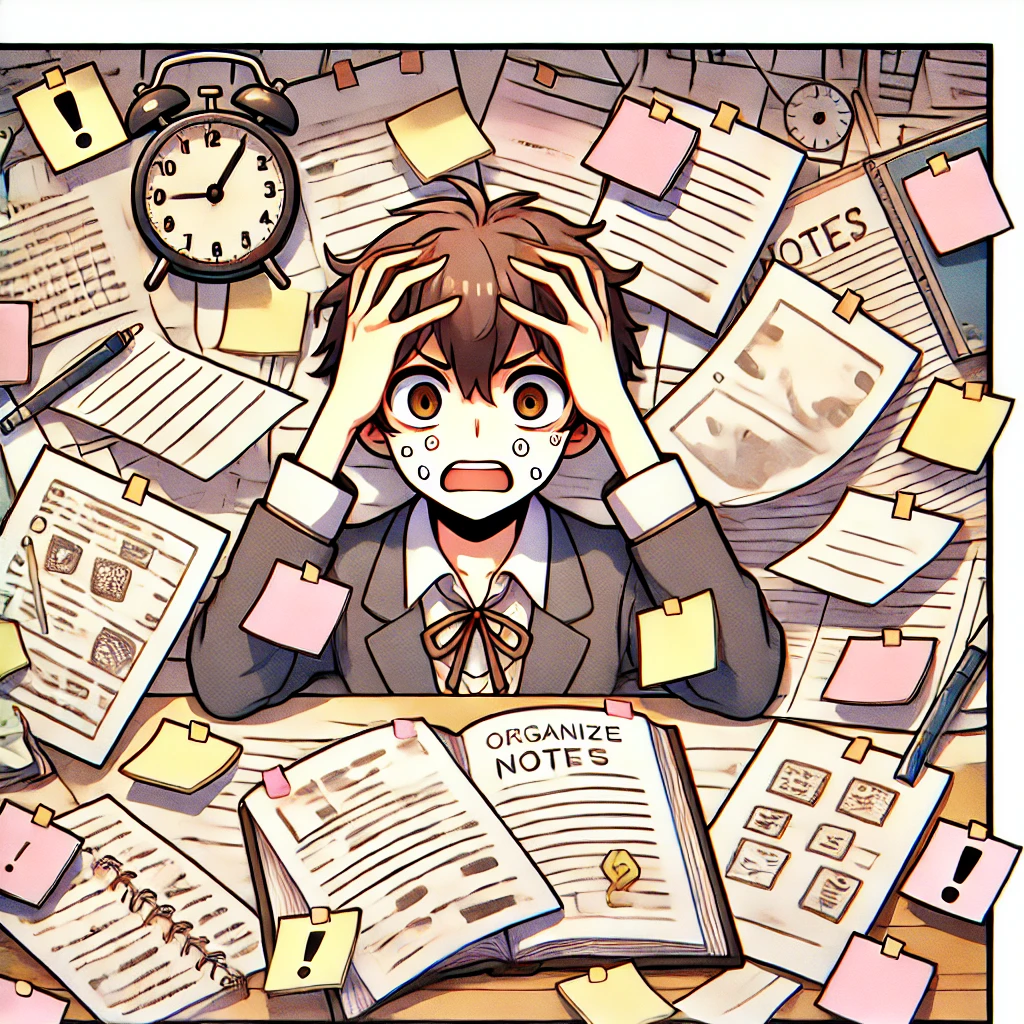
もうひとつは、「書いた内容をすぐに意味のあるものにしようとする人」です。
メモをとったその瞬間に、アイデアや気づきが生まれないと不安になる方もいます。
しかし、考えるための材料はあとからじっくり見返してこそ役に立つことが多いものです。
焦らず、まずは気になることを書き留めていくことが大切です。
そして、最も見落とされがちなのは「書くこと自体に慣れていないこと」です。
日頃からノートや手帳を使う習慣がない人にとって、いきなり情報をまとめたり抽象化したりするのは、ハードルが高く感じて当然です。
このように、難しさを感じる背景には、「完璧を目指す気持ち」「すぐに成果を求める姿勢」「慣れていないことへの不安」があります。
最初は思うように書けなくても、少しずつ自分のペースで続けることが、自然とメモを上達させる一番の近道です。
初心者でも迷わないメモを取るやり方
「メモの魔力」を使った書き方には、独特の流れがありますが、一度覚えてしまえば意外とシンプルです。
ここでは、初心者でも迷わず書けるように、やり方を3つのステップに分けてご紹介します。

ファクトを書くこと
最初のステップは、「ファクトを書くこと」です。ファクトとは、実際に見たこと、聞いたこと、起きたことなど、事実をそのままメモに書く部分です。たとえば「今日の会議で○○さんがこんな提案をしていた」というような内容です。このときは、難しく考えずに思った通りに書いて大丈夫です。
抽象化すること
次のステップは、「抽象化すること」です。これは、書いた事実の中から「つまりどういうことか?」を考えて言葉にする作業です。たとえば、「○○さんはお客様の立場で考えて話していた」という気づきなどがここにあたります。少し難しそうに見えますが、要するに「自分なりのまとめ」を書くイメージでOKです。
転用すること
最後のステップは、「転用すること」です。転用とは、自分の生活や仕事にどう活かせるかを考えることです。たとえば「私も説明するときは相手の立場を意識して話そう」といった行動のヒントを書きます。この部分が、メモを「知識」で終わらせず「行動」に変えるカギになります。
この3ステップ、つまり「ファクト→抽象化→転用」の順に書いていくことで、ただの記録が、自分にとって価値あるメモになります。最初から全部きれいに書けなくても大丈夫です。少しずつ練習しながら、自分のやりやすい形を見つけていきましょう。
抽象化が難しいと感じる原因とは
上記で少し触れましたが、メモの魔力を実践する中で、多くの人がつまずきやすいのが「抽象化」の部分です。
なぜ難しく感じるのでしょうか?
その原因のひとつは、「正解を求めすぎてしまうこと」です。
抽象化は、自分なりに「これはどういう意味だろう?」と考える作業です。
でも、学校の勉強のように「これが正しい答えです」と言われるわけではないので、不安になってしまう人も少なくありません。
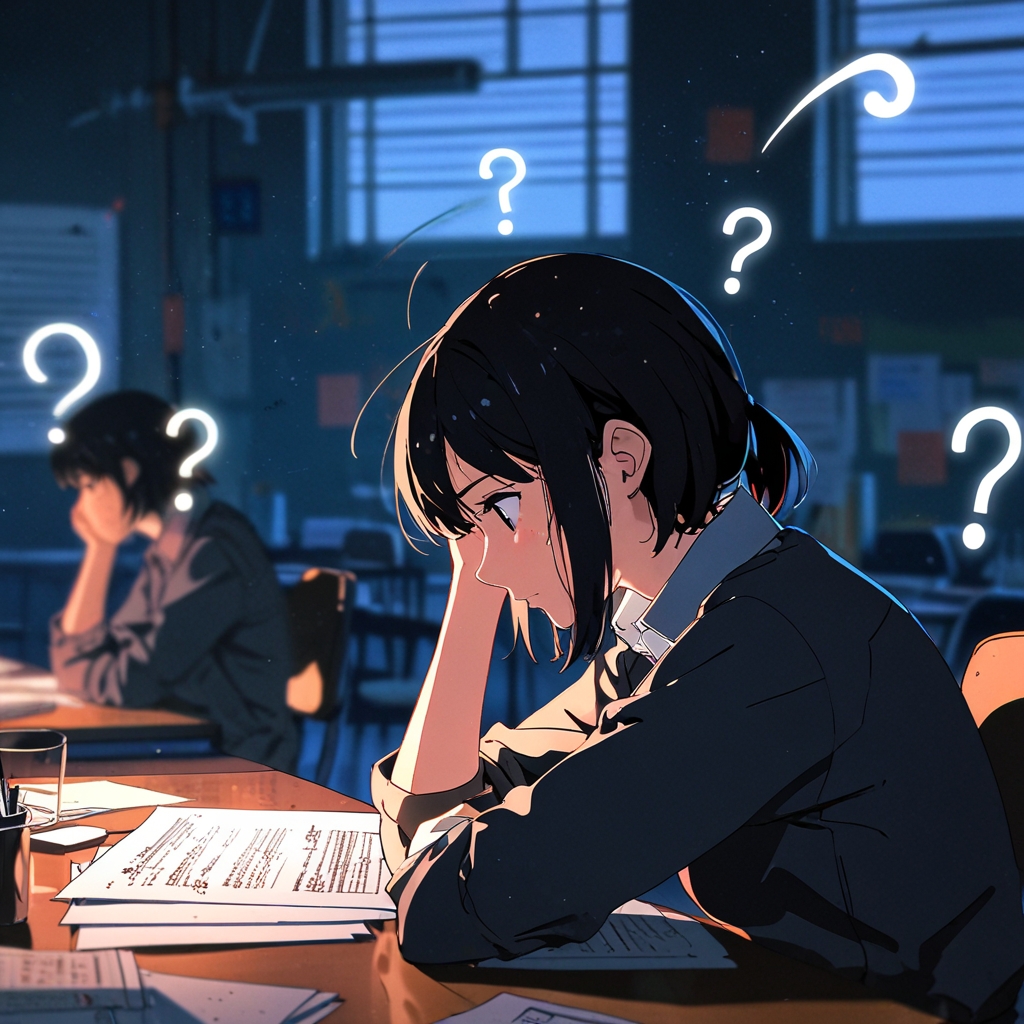
もう一つの原因は、「いきなり大きなテーマを扱おうとすること」です。
たとえば、ほんの小さな出来事に対して、「これって社会全体にどうつながるんだろう?」と考えると、難しく感じてしまいます。
抽象化は、身近な気づきからで十分です。
「これは〇〇にも通じるな」くらいの軽い気持ちで考えてOKです。
また、「そもそも抽象化のやり方を知らない」ことも大きな理由です。
抽象化とは、簡単に言えば「いろいろな場面で使える共通点を見つけること」です。
たとえば、「バスでお年寄りに席をゆずる人を見た」という出来事から、「思いやりのある行動は見ている人の心にも残る」と気づければそれが抽象化です。
このように、抽象化は練習が必要なスキルです。
最初から完ぺきにできる人はいません。大切なのは「ちょっとだけ広く考えてみよう」と意識すること。
くり返していくうちに少しずつ考え方が慣れてきます。
気軽に自分のペースで続けてみましょう。
自己分析に役立つテンプレート紹介
自己分析は、「メモの魔力」の中でも特に重要なテーマのひとつです。
しかし、いざ始めようと思っても「何から書けばいいのか分からない」と迷ってしまう人は少なくありません。
以前別記事の「書くことに迷わないジャーナリングの書き方とテーマ例30選」でも似たようなことを書きましたが、そんなときは、テンプレートを使うことをおすすめします。
テンプレートを使うと、毎回ゼロから考える必要がなくなり、自然と書く内容が決まっていきます。

これは特に初心者にとって大きな助けになります。まず基本となるのは、自己分析に適した4つの質問です。
- 思い出に残っている出来事は?
- なぜそれが印象に残っているのか?
- そのとき自分はどう感じたのか?
- そこからどんな価値観や考え方が生まれたのか?
この流れにそって答えることで、自分がどんな人間なのか、どんな価値を大切にしているのかが少しずつ見えてきます。
前田裕二さんの本には、こうした質問が1000問近く用意されており、その中から好きなものを選んで書いていくのもおすすめです。
一方で、毎日の出来事を振り返って簡単にメモするためのテンプレートも存在します。
- 今日気づいたことは?
- なぜそう思ったのか?
- 明日どう活かせそうか?
この3つの質問は、自己分析に加えて行動にもつなげやすい実用的なテンプレートです。
特に忙しい日でも、このように短く区切って書けば負担が少なく、続けやすくなります。
さらに、「曜日ごとにテーマを変える」という工夫も効果的です。たとえば月曜日は仕事、水曜日は人間関係、金曜日は趣味についてなど、テーマを決めておくと「何を書けばいいか分からない」という迷いが減ります。
ただし、テンプレートにこだわりすぎると、自由に書く楽しさが失われることがあります。
気が乗らない日や忙しいときは、箇条書きや短文でまとめても問題ありません。
無理せず続けることが、最終的には一番大切です。
このように、自分に合ったテンプレートをうまく活用することで、メモが自己分析の強力な味方になります。
正解を求めすぎず、まずは「書いてみる」ことから始めてみましょう。
続けるうちに、自分の内面が少しずつクリアになっていくはずです。
メモの魔力を意味ないものにしないノートへのメモの書き方・使い方
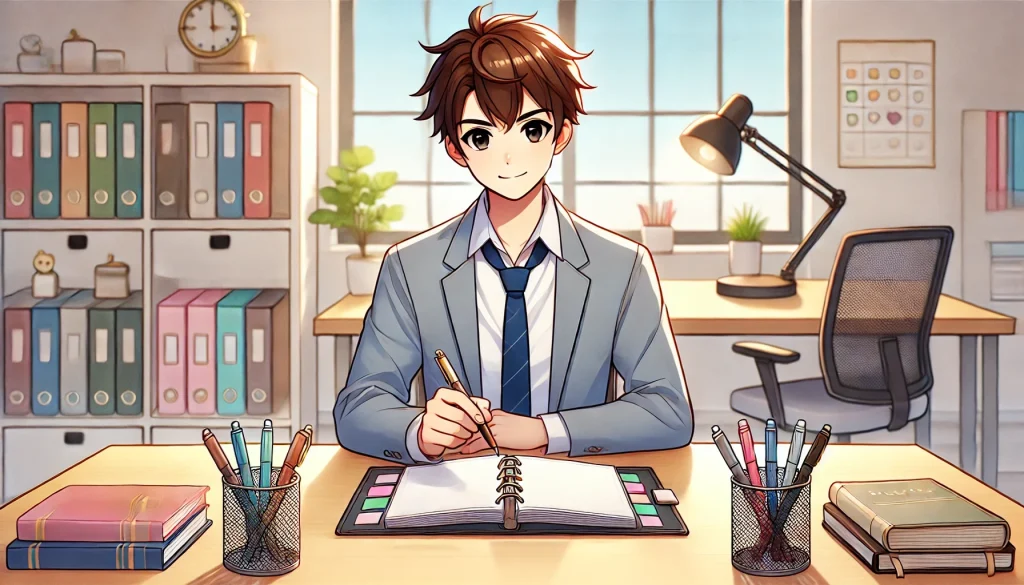
- おすすめするノートの使い方と活用術
- ノートサイズの選び方
- メモを習慣化するメリットと効果
おすすめするノートの使い方と活用術
メモの魔力を実践するために、ノートをどう使うかはとても大切なポイントです。
ただ書くだけではなく、工夫することでノートがもっと役立つようになります。
おすすめの使い方のひとつは、「ページを見開きで使うこと」です。
左側のページには事実(ファクト)を、右側には気づきや行動アイデアを書くようにすると、自然と考えが深まります。
このレイアウトにすることで、情報と自分の考えを整理しやすくなるのです。

もうひとつの活用術は、「色を使い分けること」です。
例えば、黒は事実、赤は重要なこと、緑は自分の気持ち、といったように使い分けると、後から見返したときにパッと内容がわかりやすくなります。
特に、赤で書いた部分は復習したいときにとても役立ちます。
また、ノートに書く前に何について書くかを決めておくと、迷わずにスタートできます。
「会議の内容」「今日の出来事」「読んだ本の感想」など、テーマを絞っておくだけで集中しやすくなります。
ただし注意したいのは、「完璧に書こうとしすぎないこと」です。
見た目をきれいに整えることに時間をかけすぎてしまうと、本来の目的である思考の整理が後回しになってしまうことがあります。
ノートは自分のためのツールなので、人に見せる必要はありません。
書きたいことを自由に書いていくことが大切です。
このように、ノートの使い方を少し工夫するだけで、メモの効果はぐんと高まります。
続けやすく、振り返りやすいノート作りを目指してみてください。
ノートサイズの選び方
メモを習慣にしようと思っても、「なかなか続かない…」と感じる原因のひとつが、ノートのサイズ選びです。
実は、自分に合ったサイズを選ぶことは、挫折しにくくなるための大事なポイントです。
ノートが大きすぎると、書くスペースが多くて「全部埋めなきゃ」とプレッシャーを感じてしまうことがあります。
一方で、小さすぎると書きたいことが入りきらず、かえってストレスになることもあります。
だからこそ、自分の生活スタイルや書く量に合ったサイズを選ぶことが大切です。
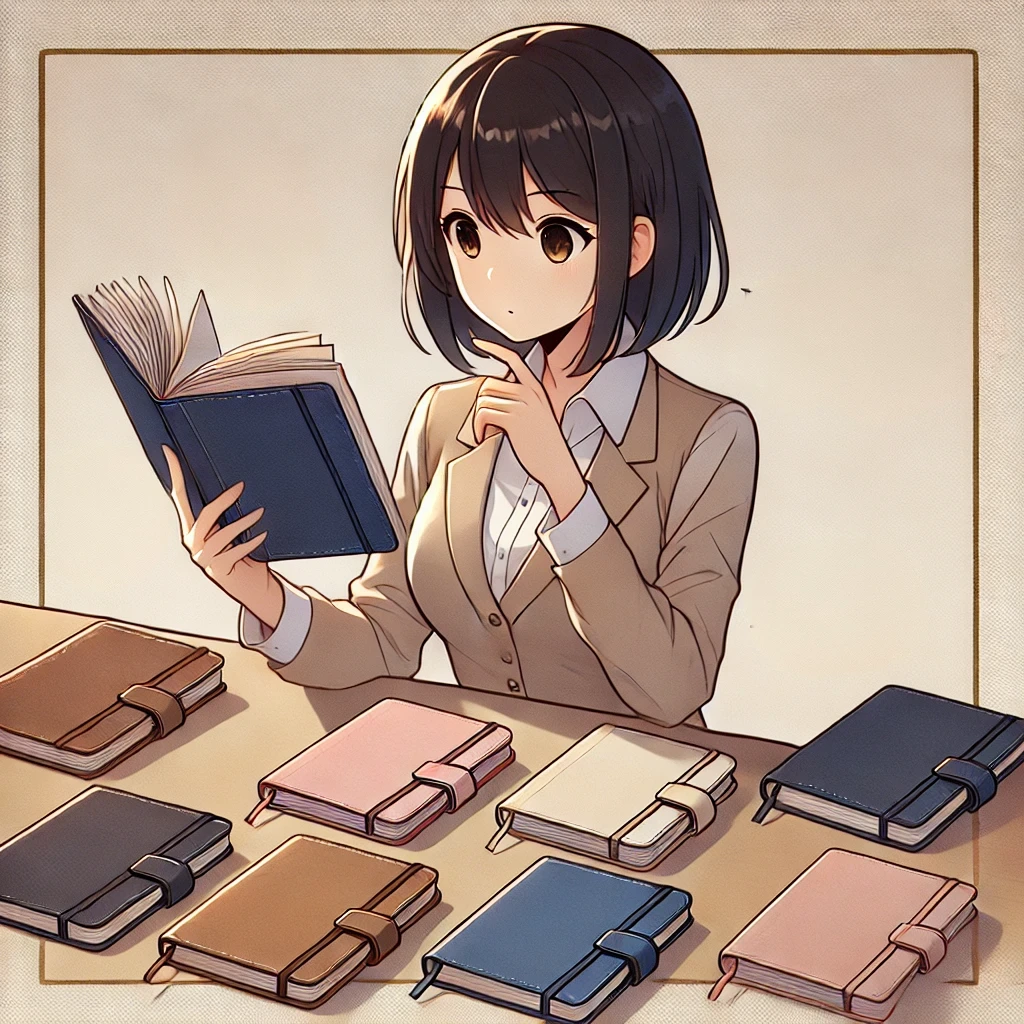
たとえば、バッグに入れて持ち歩きたい人には、A6サイズやB6サイズのコンパクトなノートがおすすめです。
カフェや電車の中でもサッと取り出して書けるので、気軽に続けやすくなります。
逆に、じっくり時間をとって書くのが好きな人には、A5やB5サイズのような少し大きめのノートのほうが、のびのび書けて気持ちも落ち着きます。
もうひとつのコツは、「気に入ったノートを使うこと」です。
お気に入りの表紙デザインや書き心地の良い紙質を選ぶだけでも、使いたくなる気持ちが高まります。
そうした書くのが楽しみになる工夫は、習慣化の強い味方です。
注意点として、高級すぎるノートは選ばないようにしましょう。
もったいなくて書けないという気持ちが出てきて使いづらくなってしまうからです。
初めは気軽に使えるノートを選んで、たくさん書くことを優先しましょう。
自分にとってストレスの少ないサイズとデザインのノートを選ぶことで、メモを続けるハードルはぐっと下がります。
道具選びも立派な準備のひとつ。
楽しく始めるための第一歩として、ぜひ自分にぴったりのノートを探してみてください。
メモを習慣化するメリットと効果
「メモを習慣にするのに意味あるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
でも実際に取り組んでみると、さまざまな良い変化が感じられるようになります。
まずひとつ目のメリットは、「自分の考えが整理されること」です。
頭の中でモヤモヤしていたことを言葉にすることで、「本当はこう思っていたんだ」と気づくことがよくあります。
何となく感じていた不安や悩みも、書き出すことでスッキリすることが多いのです。

二つ目は、「アイデアが増えること」です。
毎日、何気なく過ごしているときにも、小さなヒントや気づきはたくさんあります。
メモをとるようになると、そうした気づきを逃さずキャッチできるようになります。
そして、その中から新しいアイデアが生まれることもあるのです。
三つ目のメリットは、「自分の成長を感じられること」です。
何日か、何週間か、メモを続けて読み返してみると、あのときよりも深く考えられるようになっていると気づくことがあります。
これは、毎日少しずつでも考えを積み重ねてきた証です。
また、メモをすることで相手の話を丁寧に聞く習慣も身につきます。
話を聞きながらメモをとることで、内容をしっかり理解しようとする姿勢が自然と育つからです。
これは仕事や人間関係でも大きな強みになります。
もちろん、すぐにすべての効果を感じるわけではありません。
最初は小さな気づきでも、続けることでじわじわと実感できるのがメモの魔力の魅力です。
自分の中で変化を感じたとき、それがやってよかったと思える瞬間になるはずです。
メモの魔力が意味ないと感じる人に向けてノートへの正しいメモの書き方をまとめます
ここまでの内容を箇条書きでまとめます。
- メモの魔力は記録ではなく思考を深める道具である
- ファクト→抽象化→転用の流れが基本構造である
- メモを見返さないと意味がないと感じやすくなる
- 急いで書くと内容が曖昧で後から理解できなくなる
- 完璧なメモを目指すと逆に継続が難しくなる
- 正解を求める姿勢が抽象化を困難にする要因である
- 小さな出来事から考える癖が抽象化の第一歩になる
- 書く習慣がない人ほど最初の一歩が重く感じる
- 自己分析には質問形式のテンプレートが有効である
- テンプレートを使うことで迷わず書き始められる
- 見開きでノートを使うことで思考と行動を整理しやすくなる
- 色分けで情報の優先度が視覚的に把握しやすくなる
- ノートサイズ選びは継続性に影響を与える重要項目
- 高価なノートより気軽に使えるものが習慣化しやすい
- 書くことで思考が整理され自己成長を実感できる