「気づけばスマホを何時間も見ていた」「手元にないと落ち着かない」そんな経験はありませんか。
私たちの生活に深く浸透したスマートフォンですが、その便利さの裏側で、心身に様々な影響を与えている可能性が指摘されています。
実際、スマホ断ちの過ごし方を意識してデジタルデバイスとの上手な付き合い方を模索する人が増えています。
スマホがメンタルや脳に与える影響を考えると、スマホ断ちがもたらす効果は決して無視できません。
中には、スマホやめたら人生変わったという大きな変化を感じる人もいます。
しかし、いざ挑戦しようとしてもスマホ見ない人は何してるのだろうとか、結局何もしない時間が増えてしまうのではとか、不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、スマホを触らないようにするアプリやツールの活用法から、海外で広がるスマホ離れ、特にヨーロッパの事例、そして実際に取り組む上で困ることまで、多角的な視点からまとめてみました。
もちろん、生活から完全にスマホを絶つことを推奨するわけではありませんのでご安心を。
あなたに合った方法を見つけ、より豊かな時間を手に入れるための一歩を踏み出してみませんか。
- スマホが心身に与える具体的な影響
- スマホ断ちで得られるメリットと効果
- 「やることない」を解消する具体的な過ごし方
- スマホ断ちをサポートする便利なツールや注意点
スマホ断ちはなぜ必要?その効果から日常の過ごし方を変えた方がいい理由

- スマホがメンタルや脳に与える影響
- 海外で進むスマホ離れとヨーロッパの事例
- スマホ断ちで期待できる嬉しい効果
- スマホやめたら人生変わったという声も
スマホがメンタルや脳に与える影響

スマートフォンは非常に便利なツールですが、その過度な使用は私たちの心と脳に少なくない影響を与えることが分かってきています。
特に問題視されているのが、「デジタル依存」とそれに伴う脳疲労です。
情報過多による脳の疲労
私たちはスマホを通じて、SNSのタイムライン、ニュース、動画など、絶え間なく流れてくる膨大な情報に常にさらされています。
脳はこれらの情報を処理するために常に働き続ける必要があり、意識しないうちに疲労が蓄積していくのです。
この状態が続くと、集中力の低下や思考力の減退を招くことがあります。
本来、休息すべき時間にも情報を取り入れ続けることで、脳が十分に休まらず、慢性的な疲れを感じるようになるでしょう。
 かげとら
かげとら私自身、目が疲れたと感じることはありますが、脳が疲れたと感じることは感じたことはありません。意識できないからこそ、意識的に気をつけなければいけないのかもしれません。
ブルーライトと睡眠の質の低下
多くの人が就寝前にベッドの中でスマホを見ていますが、これは睡眠の質を著しく低下させる原因となります。
スマホの画面が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制する働きがあるためです。
メラトニンの分泌が妨げられると、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。
結果として、十分な睡眠時間を確保しても疲れが取れず日中のパフォーマンス低下につながるのです。
(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」)



就寝前の1〜2時間はスマホの使用を控えるだけで、睡眠の質は大きく改善される可能性があるそうです!
ドーパミンによる依存の形成
SNSで「いいね」をもらったり、ゲームをクリアしたりすると、脳内では「ドーパミン」という快楽物質が分泌されます。
これは達成感や幸福感をもたらしますが、同時に強い依存性を持ちます。
スマホはこのドーパミンを手軽に、そして、繰り返し得られるように設計されているのです。
このため、私たちはより強い刺激を求めて無意識のうちにスマホを触り続けてしまいます。
これが「スマホ依存」の正体であり、スマホがないと不安になったりイライラしたりする状態はこのドーパミン回路が大きく関係しています。
このように、スマホの長時間使用は私たちの集中力、睡眠、そして精神的な安定にまで影響を及ぼします。
これらの事実を理解することが、スマホとの健全な付き合い方を考える第一歩となるでしょう。
海外で進むスマホ離れとヨーロッパの事例
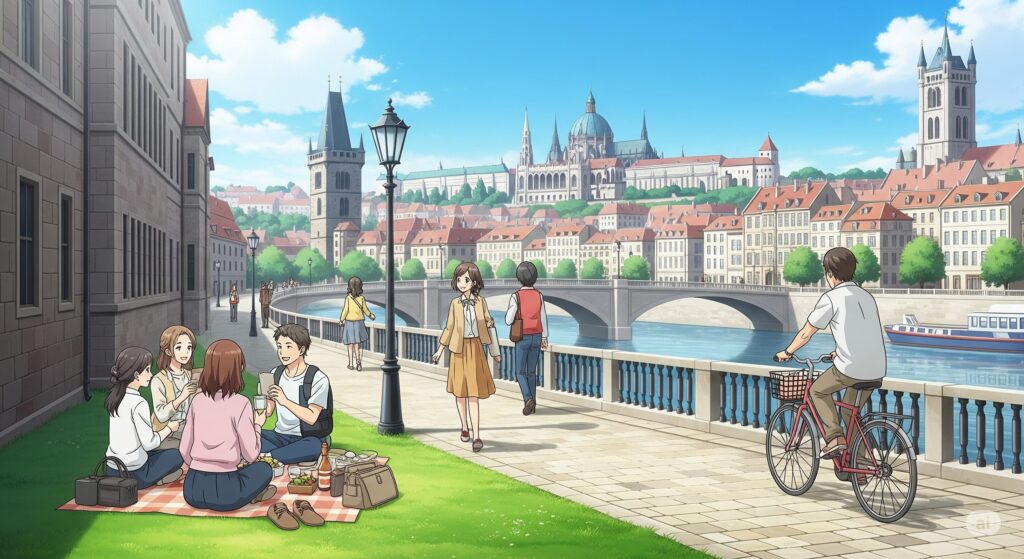
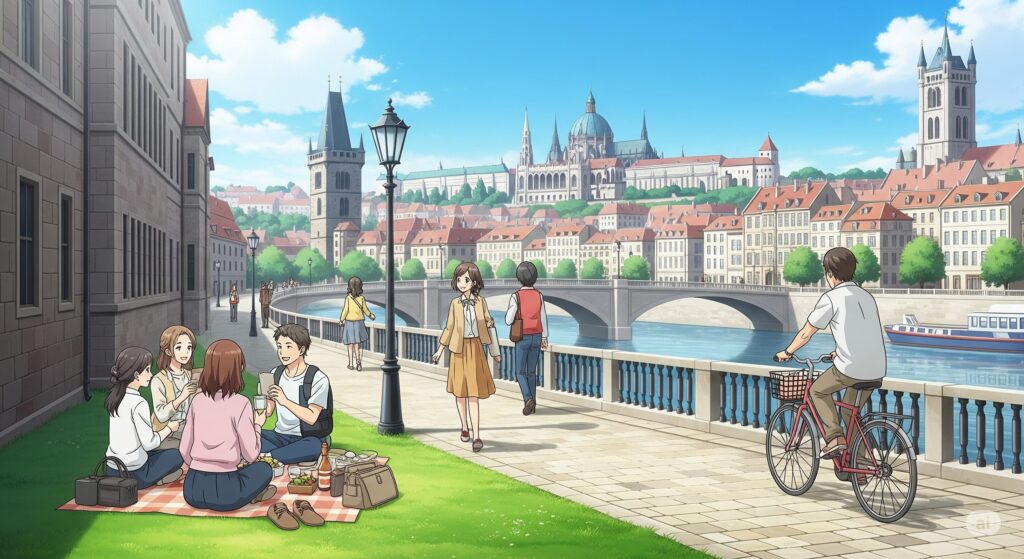
スマートフォンの影響に対する懸念は、日本だけでなく世界共通の課題です。
特にヨーロッパ諸国では、子どもたちを過度なデジタル情報から守るため、社会全体で「スマホ離れ」を推進する動きが活発化しています。
「スマホ依存は自分だけの悩みだと思っていたけど、世界的な課題だったんだな…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
具体的な事例を知ることで、スマホとの距離感を考える新たな視点が得られますよ。
イギリスの保護者たちが始めた草の根運動
イギリスでは、保護者たちが主導する「Smartphone Free Childhood(スマホのない子ども時代)」という草の根運動が大きな広がりを見せています。
(公式サイト:Smartphone Free Childhood)
これは、「周りが持っているから」という同調圧力に流されるのではなく「少なくとも14歳頃まではスマホを持たせない」という選択肢を社会の常識にしようという取り組みです。
一個人の力では難しいことも、地域や学校単位で保護者が連携することで、子どもたちがスマホを持たない環境を自然に作ることができます。
この運動はSNSを通じて急速に拡大し、テクノロジーとの付き合い方を社会全体で問い直すきっかけとなっています。
フランスやデンマークにおける法的な規制
国レベルでの対策に乗り出している国もあります。
例えば、フランスでは2018年から、小学校および中学校でのスマートフォンの使用が法律で原則禁止されました。
生徒の集中力を維持し、ネットいじめなどのトラブルを防ぐことが目的です。
また、デンマークも2025年から学校でのスマホ使用を禁止する方針を発表するなど、教育現場からデジタルデバイスを切り離す動きはヨーロッパ全体で加速しています。
これは、子どもの健全な発達のためには、オフラインでのコミュニケーションや学びが不可欠であるという考えに基づいています。
さらに、企業側にもユニークな動きがあります。
ビールメーカーのハイネケンは、SNSなどができない通話機能中心のシンプルな携帯電話「The Boring Phone(たいくつなケータイ)」を発表し話題となりました。
(参照:ASCII.jp 「ハイネケンがSNS不可な世界一退屈なケータイを発売! デジタルデトックスに最適だ!」)
これは、仲間との楽しい時間をスマホに邪魔されず、現実のコミュニケーションに集中してほしいというメッセージが込められています。
これらの事例からわかるように、スマホとの距離を置くことは、個人の意志だけで頑張るものではなく、社会やコミュニティ全体で取り組むべき課題として認識されつつあります。
日本にいる私たちも、こうした世界の動向から学ぶことは多いはずです。
スマホ断ちで期待できる嬉しい効果


スマホとの距離を意識的に置く「スマホ断ち」を実践すると、私たちの生活にはどのような良い変化が訪れるのでしょうか。
多くの場合、心身の健康改善や、時間の使い方の質的向上といった、数多くのポジティブな効果が期待できます。
ここでは、スマホ断ちによって得られる代表的なメリットを具体的に紹介します。
① 睡眠の質が劇的に向上する
前述の通り、スマホ画面のブルーライトは睡眠の質を低下させる大きな原因です。
そのため、就寝前の時間だけでもスマホ断ちを実践することで、寝つきが良くなり深い眠りを得やすくなります。
質の高い睡眠は日中の集中力や気分の安定に直結します。
朝、すっきりと目覚められるようになり、一日を活動的に過ごすためのエネルギーが満ちてくるのを感じられるでしょう。
② 集中力が戻り生産性が上がる
スマホが近くにあるだけで、私たちは無意識に通知を気にしてしまい集中力が散漫になりがちです。
スマホを物理的に遠ざけることで、目の前の仕事や勉強に深く没頭できるようになります。
集中力が持続するようになると、作業効率は格段に向上します。
これまで何時間もかかっていたタスクが、より短い時間で完了できるようになるかもしれません。
これは、仕事や学業において大きなアドバンテージとなります。
③ ストレスが軽減され心が軽くなる
SNSは他者と繋がれる便利なツールですが、一方で他人と自分を比較して落ち込んだり、ネガティブな情報に触れて疲弊したりする「SNS疲れ」の原因にもなります。
スマホ断ちは、こうした不要な情報から自身を守るための有効な手段です。
他人の動向を気にする時間が減ることで、精神的なストレスが大幅に軽減されて心が穏やかになるのを感じるはずです。
自分自身の感情や価値観と向き合う時間が増え、心の健康を取り戻すことにつながります。
④ 自由な時間が増え新しい発見がある
通勤中や休憩時間など、何気なくスマホを眺めていた「スキマ時間」。
これらの時間を合計すると、1日で相当な時間になります。
スマホ断ちをすることで、この時間が「自由に使える時間」として生まれます。
その時間を読書や勉強、趣味、あるいは散歩などに使うことで生活はより豊かになります。
普段は気づかなかった街の風景や新しいお店の発見など、現実世界での小さな幸せに気づく余裕が生まれるでしょう。
スマホやめたら人生変わったという声も


「スマホ断ち」を継続的に実践した人たちからは、「人生が変わった」と感じるほどの大きな変化を体験したという声が数多く聞かれます。
これは単なる気分の問題ではなく、時間の使い方や物事の捉え方が根本的に変わることで、生活全体の質が向上するためです。
「人生が変わった」と聞くと大げさに聞こえるかもしれません。
しかし、これはスマホに奪われていた「時間」と「集中力」という最も貴重な資源を取り戻すことで、自己実現に向けた行動が可能になるというごく自然な結果なのです。
自分の「やりたいこと」が見つかる
スマホを眺めている時間は、受動的に情報を受け取る時間です。
この時間を減らし、自分自身と向き合う静かな時間を持つことで、「自分は本当は何がしたいのか」を深く考える機会が生まれます。
「時間がない」を言い訳にして後回しにしていたことや、心の奥底で眠っていた興味・関心に気づくことができます。
資格の勉強を始めたり、新しい趣味に挑戦したりと、自己投資や自己実現のための具体的な行動につながっていくケースは非常に多いです。
思考力が深まり物事の本質を捉えられるようになる
私たちは分からないことがあると、すぐにスマホで検索して答えを得ることに慣れてしまっています。
これは効率的に思えますが、一方で「自らじっくり考える」というプロセスを省略してしまい、思考力を低下させる一因にもなっています。
スマホから離れることで、自分の頭で粘り強く考える習慣が戻ってきます。
物事の背景や本質を深く洞察する力が養われ、仕事や日常生活における判断の質も高まるでしょう。
現実世界での人間関係が豊かになる
スマホに夢中になっていると、目の前にいる家族や友人とのコミュニケーションがおろそかになりがちです。
食事中や会話中にスマホを触らないと決めるだけでも、相手と真剣に向き合う時間が増え関係性はより深まります。
また、スマホ断ちで生まれた時間を新しい趣味やコミュニティ活動に充てることで、リアルな世界での新たな出会いも期待できます。
デジタル上の繋がりだけでなく、顔の見える温かい人間関係が日々の生活に充実感と安心感をもたらしてくれるでしょう。
最初は少し物足りなく感じるかもしれませんが、スマホから解放された先にはこれまで見過ごしていた豊かで新しい世界が広がっているはずです。
小さな一歩から人生を変える体験を始めてみませんか。
スマホ断ちした時の具体的な過ごし方と試したいアイデア


- やることないと感じた時はこう考えてみよう
- スマホ見ない人は何してる?
- 【具体例1】運動や散歩でリフレッシュする
- 【具体例2】読書や趣味に没頭する
- スマホを触らないようにするアプリやツールの活用法
- 注意点として知っておきたいスマホがないと困ること
やることないと感じた時はこう考えてみよう


スマホ断ちを始めた多くの人が最初に直面する壁が、「やることがない」という感覚です。
これまで無意識にスマホで埋めていた時間の空白が急に目の前に現れるため、手持ち無沙汰に感じてしまうのは自然なことです。
しかし、この感覚はネガティブなものではありません。
むしろ、自分の時間を主体的に使うチャンスが訪れたサインと捉えることができます。
ここでは、「やることない」を乗り越えるための意識改革のヒントをいくつか紹介します。
「時間の浪費」から「時間の投資」へ
時間の使い方には、大きく分けて2種類あります。
一つは、特に目的もなくSNSや動画を眺めるような「時間の浪費」。
もう一つは、将来の自分につながる読書や勉強、スキルアップのような「時間の投資」です。
スマホ断ちで生まれた時間を、ぜひ後者の「時間の投資」に充てることを意識してみてください。
たとえ5分や10分といった短い時間でも、単語を一つ覚える、ストレッチをするなど、自分のためになる行動を積み重ねることが大切です。
この意識を持つだけで、時間の価値が大きく変わってきます。
「Time is money(時は金なり)」という言葉があります。
これは、時間がお金と同じように貴重なものであることを示す有名な格言です。
スマホ断ちは、この貴重な時間をどう使うかを見直す絶好の機会なのです。
「何もしない時間」を積極的に楽しむ
現代人は、常に何かをしていないと不安を感じがちです。
しかし、時には意図的に「何もしない時間」を作ることも重要です。
ぼーっと窓の外を眺めたりお茶を飲みながら深く呼吸をしたりする時間は、疲れた脳を休ませ思考を整理するために非常に有効です。
スマホがないと最初は退屈に感じるかもしれません。
しかし、その静けさの中で、新しいアイデアが浮かんだり、自分の本当の気持ちに気づいたりすることがあります。
「退屈」を恐れず、創造的な空白の時間として受け入れてみましょう。
小さな「やりたいことリスト」を作る
「やることない」と感じるのは、具体的な代替案がすぐに思い浮かばないからです。
そこで、あらかじめ「スマホがない時にやりたいこと」をリストアップしておくことをおすすめします。
「気になっていたカフェに行く」「部屋の模様替えをする」「手紙を書く」など、些細なことで構いません。
リストが手元にあれば、スキマ時間ができた時に迷わず行動に移せます。
リストを作る行為自体が、自分の興味関心を探る良い機会にもなるでしょう。
スマホ見ない人は何してる?


「スマホを手放した時間を、具体的にどう過ごせばいいの?」というのは、多くの人が抱く疑問です。
スマホを見ていた時間を有意義なものに変えるためには、意識的に別の活動を取り入れる必要があります。
ここでは、スマホがないからこそ楽しめる、おすすめの活動カテゴリーをいくつかご紹介します。
これらのアイデアを参考に、自分に合った過ごし方を見つけてみてください。
① 五感を使うクリエイティブな活動
デジタル情報から離れて自分の手や体を使って何かを創り出す活動は、脳に良い刺激を与え高い満足感をもたらします。
- 料理・お菓子作り
レシピを見ながら新しいメニューに挑戦したり、手間のかかる料理にじっくり取り組んだりする。 - 絵を描く・塗り絵
大人向けの塗り絵やスケッチブックで、無心に色を塗ったり線を描いたりする。 - 楽器の練習
昔習っていたピアノを再開したり、新しい楽器に挑戦したりする。 - ガーデニング
ベランダや室内でハーブや野菜を育てる。植物の成長は日々の楽しみになります。
② 心と体を整えるフィジカルな活動
体を動かすことは、ストレス解消や気分のリフレッシュに非常に効果的です。
スマホを見ている時の前傾姿勢で固まった体をほぐしましょう。
- 散歩・ウォーキング
普段通らない道を歩いてみる。目的もなく歩くだけで新しい発見があります。 - ヨガ・ストレッチ
自宅で動画を見ず、自分の体の声に耳を傾けながらゆっくりと体を伸ばす。 - 筋力トレーニング
ジムに通うだけでなく自重トレーニングなど自宅でできることから始める。 - 掃除・片付け
部屋が綺麗になると、心もスッキリします。断捨離もおすすめです。
③ 自分を成長させる自己投資活動
スマホ断ちで生まれた時間を、将来の自分のための「投資」として活用するのも素晴らしい過ごし方です。
- 読書
積読になっていた本を読む。電子書籍ではなく紙の本をめくる体験も新鮮です。 - 資格の勉強
興味のある分野の勉強を始める。集中できる環境が整い、学習効率が上がります。 - ジャーナリング(日記)
その日感じたことや感謝したことをノートに書き出す。自己分析につながります。 - 瞑想(マインドフルネス)
5分間、静かに座って呼吸に意識を向ける。思考が整理されて集中力が高まります。
これらの活動に共通するのは、今、ここに集中するということです。
スマホを使っている時は意識が常に外部に向いていますが、これらの活動は意識を自分自身や目の前の物事に向ける手助けをしてくれます。
ぜひ、興味のあるものから試してみてくださいね。
【具体例1】運動や散歩でリフレッシュ


スマホ断ちで生まれた時間を活用する上で、最も手軽で効果的な方法の一つが「体を動かすこと」です。
特別な道具や場所がなくても、すぐに始められる運動や散歩は、心と体の両方に素晴らしいリフレッシュ効果をもたらしてくれます。
なぜ運動や散歩が効果的なのか
長時間スマホを見ていると、同じ姿勢が続くことで血行が悪くなりがちです。
特に首や肩の凝りに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
軽い運動や散歩は、これらの体の不調を和らげるのに役立ちます。
また、運動をすると、セロトニンという神経伝達物質が脳内で分泌されます。
セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させて気分を前向きにする効果があります。
スマホをいじって気分が晴れない時にこそ、外に出て体を動かすことが手っ取り早い気分転換になるのです。
今日から始められる具体的なアイデア
- 目的のない散歩
「どこかへ行く」という目的を持たず、ただ気の向くままに歩いてみましょう。普段気づかなかったお店、美しい花、面白い形の雲など、日常に隠れた小さな発見が、心を豊かにしてくれます。 - 一駅手前で降りて歩く
通勤や通学の際に、一駅分だけ歩く習慣をつけるのもおすすめです。無理なく日常に運動を取り入れることができます。 - 公園での軽い運動
公園のベンチでストレッチをしたり、広場で少し早歩きをしたりするだけでも十分です。自然の緑や風を感じることで、デジタルデバイスによる目の疲れも癒されます。 - ラジオ体操
子どもの頃以来やっていない方も多いかもしれませんが、ラジオ体操は全身を効率よく動かせる、非常によくできた運動です。動画に頼らず、記憶を頼りにやってみるのも面白いでしょう。
重要なのは、完璧を目指さないことです。
「毎日1時間走る」といった高い目標を立てる必要はありません。
まずは「5分だけ外に出てみる」という小さな一歩から始めてみてください。
体を動かす心地よさを一度感じられれば、それが新しい習慣へとつながっていくはずです。



散歩についてこのブログではいくつか記事を挙げているので良かったらこちらも読んでみてください。
「散歩が趣味ってやばいの?知らなきゃ損する驚きのメリット!」
「散歩が好きな人の性格から人生を好転させる秘訣を学ぶ」
「予定もルールもいらない!一人散歩の楽しみ方」
【具体例2】読書や趣味に没頭する
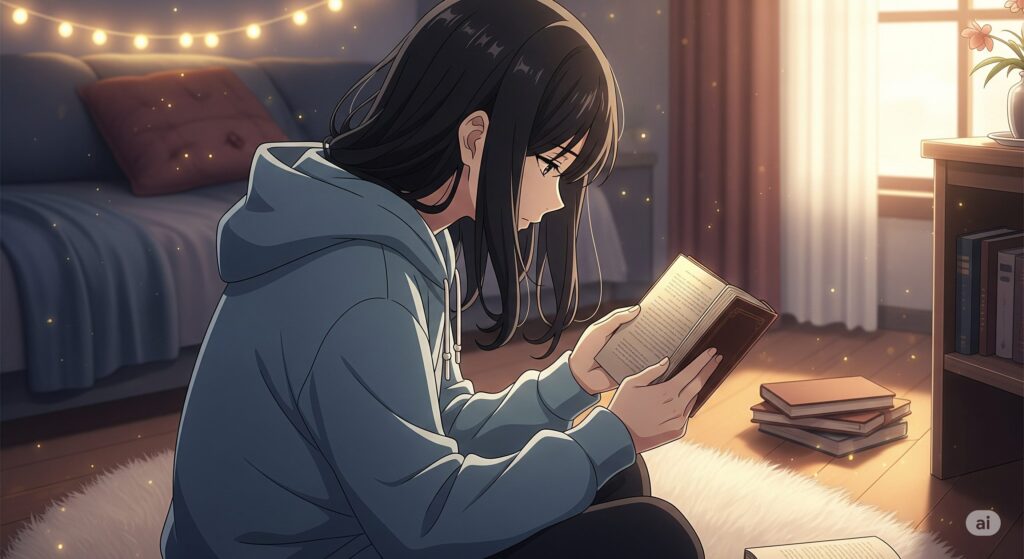
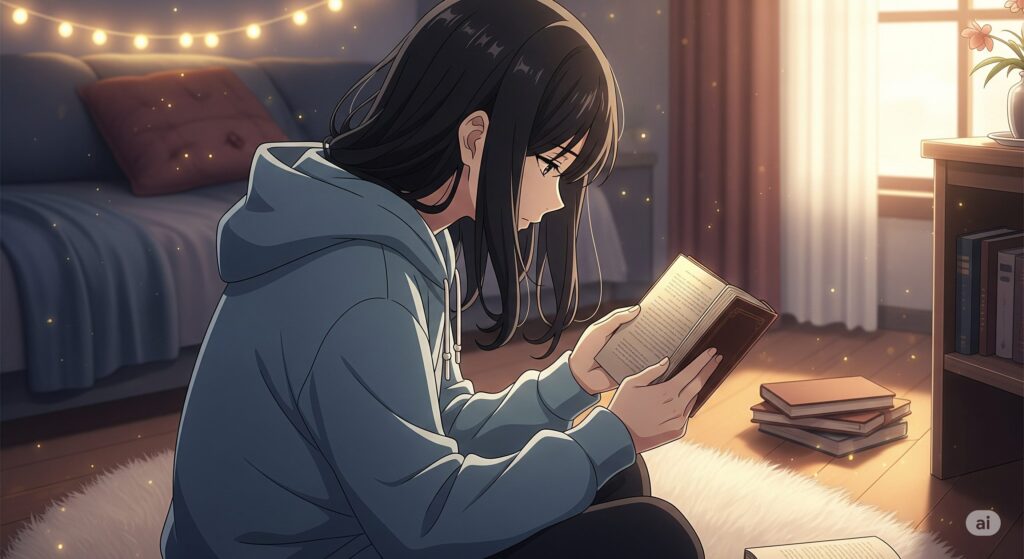
スマホの魅力が「短時間で手軽な快楽」であるならば、その対極にあるのが「時間をかけて深く没頭する体験」です。
読書や趣味にじっくりと取り組む時間は、スマホでは得られない質の高い充実感と心の栄養を与えてくれます。
スマホ断ちで生まれた静かな時間をあなただけの豊かな世界を広げるために使ってみませんか。
なぜ読書や趣味への没頭が有効なのか
読書や趣味に集中している時、私たちの脳は「フロー状態」と呼ばれる極めて高い集中状態に入ることがあります。
この状態では、時間の感覚がなくなり目の前の活動に完全に没入します。
フロー状態は、強い幸福感や達成感をもたらすことが科学的にも知られています。
絶え間ない通知や情報で集中が途切れがちなスマホの世界とは異なり、一つの物事に深く没頭する体験は散漫になった思考をまとめ、精神的な安定を取り戻すのに非常に効果的です。
没頭できる時間を作るためのヒント
「集中できる趣味がない」と感じる方もいるかもしれません。
大切なのは、最初から完璧な作品を作ろうとしたり難しい本を読もうとしたりしないことです。
自分が「少し楽しい」「ちょっと心地よい」と感じることから始めるのが、没頭への入り口です。
- 紙の本に触れる
電子書籍も便利ですが、あえて紙の本を選んでみましょう。紙の質感やインクの匂い、ページをめくる音は、五感を刺激し、読書体験をより豊かなものにします。図書館に足を運び、偶然の本との出会いを楽しむのも素敵です。 - 「ながら」ではない音楽鑑賞
作業用のBGMとしてではなく、音楽を聴くこと自体を目的とした時間を作ってみましょう。ソファに座って目を閉じ、歌詞や楽器の音色一つひとつにじっくりと耳を傾けることで、 - プロセスを楽しむ趣味
料理やプラモデル、手芸などは、完成形だけでなく、その過程(プロセス)自体に楽しみがあります。手順を一つひとつ丁寧に行うことに集中することで、雑念が消え、心が落ち着きます。 - 知識を探求する
歴史、宇宙、芸術など、自分が純粋に「知りたい」と思える分野について、本や資料を使って深く掘り下げてみるのも良いでしょう。断片的なネット情報とは違う、体系的な知識を得る喜びは格別です。
スマホから離れることで初めて、私たちは自分が本当に好きなこと時間を忘れて夢中になれるものと出会えるのかもしれません。
それは、あなた自身の人生をより深く色鮮やかにするための大切な時間となるはずです。



読書についてこのブログでは以下の記事を挙げていますのでこちらも読んでもらえると嬉しいです。
「読書はつまらない?趣味にしたいけどできない理由と苦手意識を変えるコツ」
「読書が苦手な大人におすすめしたい本との接し方と本嫌いでも読める本」
スマホを触らないようにするアプリやツールの活用法


スマホから離れるためのアプリ
「自分の意志だけでは、ついついスマホを触ってしまう…」そんな方のために、スマホ断ちをサポートしてくれる便利なアプリが存在します。
矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、スマホの機能を逆手に取ってスマホから離れる習慣を作るのです。
ここでは、スマホ依存対策として人気のあるアプリの種類とその活用法についてご紹介します。
自分に合ったツールを見つけることで、ゲーム感覚で楽しくスマホ断ちに取り組めるかもしれません。
| アプリのタイプ | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 育成・ゲーム型 | スマホを触らない時間に応じて、木や魚、キャラクターなどが育つ。途中でスマホを触るとペナルティがある。 | 楽しみながら習慣化したい人、達成感をモチベーションにしたい人 |
| 強制ロック型 | 設定した時間、特定のアプリやスマホ自体を完全にロックする。時間内は物理的に操作できなくなる。 | 意志の力に自信がない人、試験勉強など絶対に集中したい期間がある人 |
| 時間計測・可視化型 | アプリごとの使用時間やスマホを起動した回数を記録・分析してくれる。客観的なデータで自分の使い方を把握できる。 | まずは自分の現状を知りたい人、データに基づいて改善計画を立てたい人 |
以下に具体的なアプリを紹介しておきます。
- Forest (育成・ゲーム型)
スマホを触らない時間を設定すると、アプリ内で木が育ち始めます。設定時間内に他のアプリを開いたりすると、木が枯れてしまうというシンプルなルールです。自分が集中した時間だけ森が豊かになっていくのが目に見えるため、継続するモチベーションにつながります。 - スマホ依存タイマー (強制ロック型)
カウントダウンタイマーをセットすると、時間がゼロになるまでスマホが完全に操作不能になります。非常に強力なため、「この時間だけは絶対に集中する」という強い意志がある時に有効です。 - スクリーンタイム / Digital Wellbeing (時間計測・可視化型)
これらはiPhoneやAndroidに標準で搭載されている機能です。自分がどのアプリにどれだけの時間を使っているかを正確に把握できます。「なんとなく使いすぎている」という感覚を、ことが、行動を変える第一歩になります。アプリごとに使用時間制限をかけることも可能です。
注意点
これらのアプリはあくまで補助的なツールです。アプリを入れるだけで満足せず、「なぜスマホ断ちをしたいのか」という目的意識を常に持つことが最も重要です。
これらのアプリを上手く活用し、スマホに管理されるのではなく、自分がスマホを管理する、という主体的な関係を築いていきましょう。
最終手段!物理的に遮断するタイムロッキングコンテナ
「アプリの制限だけでは、結局アンインストールしたり、設定を無視したりしてしまう…」という方もいるでしょう。
そんな方のためにより強力な強制力を求める方におすすめなのが「タイムロッキングコンテナ」です。
これは、タイマー付きのプラスチック製の箱で、中にスマートフォンなどを入れてタイマーをセットすると、設定した時間になるまで物理的に開けることができなくなります。
意志の力に頼ることなく強制的にスマホから距離を置く環境を作り出せるため、誘惑そのものを断ち切りたい場合に非常に有効なツールです。
勉強や仕事に集中したい時間、あるいは、家族と過ごす大切な時間など絶対にスマホを触りたくない時間帯に活用することで、絶大な効果を発揮するでしょう。
通常のタイムロッキングコンテナは設定した時間内はスマホに触れなくなってしまい、緊急連絡時の対応もできなくなってしまうのですが、上記の商品はかかってきた電話には出ることができるような仕様になっているので、心配な方はこちらの商品を使ってみるのをおすすめします。
注意点として知っておきたいスマホがないと困ること


スマホ断ちには多くのメリットがあるのは上記の説明でわかっていただけたと思います。
しかし、現代社会においてスマホが生活インフラの一部となっている以上、手放すことで生じる不便さやデメリットも存在します。
そこで、あらかじめ「困ること」を想定して対策を考えておく必要があります。
これにより、いざという時に慌てずに挫折を防ぐことができるからです。
ここでは、スマホ断ちを実践する上で特に注意すべき点をいくつかご紹介します。
緊急時の連絡手段
最も大きな懸念点は緊急時の連絡です。
家族や職場からの急な連絡あるいは災害発生時などに、すぐに情報を受け取れなかったり連絡が取れなかったりする可能性があります。
- 対策
スマホ断ちをする時間帯や期間を、あらかじめ家族や親しい友人、職場の人に伝えておきましょう。「この時間帯は電話に出られない可能性が高い」と周知しておくだけで、相手の心配を減らすことができます。また、緊急連絡は固定電話やPCのメールにしてもらうようお願いしておくのも一つの手です。
外出先での不便さ
スマホはもはや単なる電話ではありません。
地図、交通機関の乗り換え案内、キャッシュレス決済、お店の検索など外出先での活動を支える重要なツールです。
- 対策
外出前に、目的地までのルートや電車の時刻をPCなどで調べて印刷したり、メモを取ったりしておく習慣をつけましょう。支払いも現金やクレジットカードを準備しておく必要があります。
特に初めて行く場所や、時間に遅れられない約束がある場合は、無理にスマホ断ちをせず、補助的に利用するなど柔軟な対応が必要です。目的はスマホを使わないこと自体ではなく、スマホに振り回されないことです。
情報格差や孤立感
友人間のやり取りやコミュニティの連絡が、LINEなどのSNSグループで行われている場合、スマホから離れることで情報から取り残されて孤立感を感じてしまうかもしれません。
- 対策
「重要な連絡は電話かショートメッセージでほしい」と個人的にお願いしておく、あるいは1日のうちで時間を決めてPCで確認するなど、自分なりのルールを決めて対応しましょう。また、前述の通り、スマホ断ちで生まれた時間でリアルな人間関係を深めることが、この孤立感を乗り越える鍵となります。
これらの「困ること」は、スマホがいかに私たちの生活に深く根付いているかの裏返しでもあります。
だからこそ重要なのは、生活から完全にスマホを絶つ必要はないと理解することです。
私たちの目的は、便利なツールであるスマホを完全に排除することではなくそれに振り回されずに主体的に使いこなすための「心地よい距離感」を見つけることにあります。
不便さを乗り越えた先にあるメリットを信じ自分なりの工夫で対処していくことが、スマホとの新しい関係を築く秘訣です。
最後にスマホ断ちの効果と自分に合った過ごし方についてまとめます
ここまで、スマホ断ちの効果から具体的な過ごし方、注意点についてを解説してきました。
最後にこの記事の要点をまとめます。
- スマホの過度な使用は脳疲労や睡眠の質低下を招く
- 海外、特にヨーロッパでは社会全体でスマホ離れの動きがある
- スマホ断ちの効果には集中力向上やストレス軽減などが挙げられる
- 時間の使い方を「浪費」から「投資」へ意識改革することが重要
- 「やることない」と感じたらあらかじめやりたいことリストを作る
- スマホを見ない時間は運動や散歩で体を動かすのがおすすめ
- 読書や趣味など一つのことに没頭する時間は満足度が高い
- 意志が弱い場合はスマホ依存対策アプリを活用するのも有効
- 育成ゲーム型や強制ロック型などアプリには種類がある
- 緊急連絡や外出時の不便さなど困ることも想定しておく
- 対策として周囲に事前に伝えたりPCで代用したりする
- 完璧を目指さずまずは寝る前1時間など短時間から始める
- 目的はスマホを使わないことではなく豊かな時間を取り戻すこと
- 自分にとって心地よいバランスを見つけることが最も大切
- 小さな成功体験を積み重ねて新しい習慣を築いていこう
