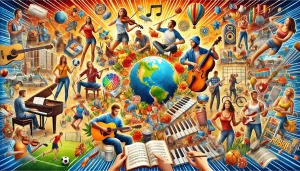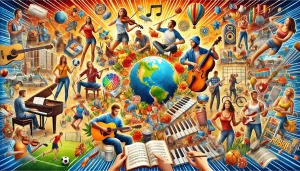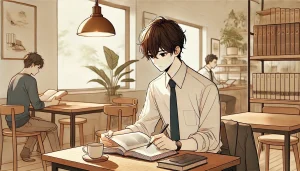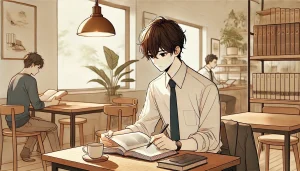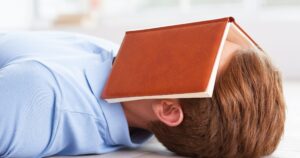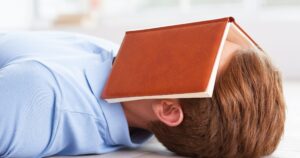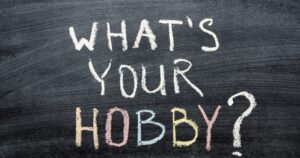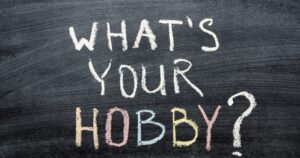最近なんだか無気力でさ・・・、何かやろうとは思うけど、趣味もないし結局ダラダラして1日が終わっちゃうんだよ



わかる!何もしなかったって自己嫌悪になるんだよね



そうそう。でも、どうしたらこの無気力を抜け出せるんだろう?
時間はあるのに何もする気にもなれず、無気力な日々が続いてしまうことがあります。
やる気を出そうと思っても、なかなかスイッチが入らず、「また何もせず1日が終わってしまった…」と落ち込むこともあるかもしれません。
でも、無気力になってしまうのには理由があります。
もしかすると、あなたが「やる気が出たら行動しよう」と思っていることが、逆に動けない原因になっているのかもしれません。
この記事では、無気力から抜け出すための小さな一歩を紹介します。
頑張る必要はありません。
気楽に読んで、できそうなことから試してみてください。
- 趣味がないと無気力になりやすい原因とメカニズム
- やる気を待たずに行動を起こすための具体的な方法
- 無気力な状態を改善するための小さな習慣や工夫
- 気分が乗らなくても楽しさを感じるコツや考え方
趣味がない人は無気力になりやすい


- 好きだったものが楽しめない…その原因は?
- 無気力の原因は「やる気の待ちすぎ」
- 何もしないのに疲れるのはなぜか
好きだったものが楽しめない…その原因は?
「昔は好きなことがあったのに、最近は何をしても楽しくない…」そんな風に感じたことはありませんか?
趣味を持ちたい気持ちはあるのに、なぜかやる気が出ない。
そんな状態が続くと、「自分はダメなのでは?」と落ち込んでしまうことも。
実は、それにはちゃんとした理由があるんです。
ここでは、何をしても楽しくないと感じる正体についてまとめてみます。


楽しめないのは「刺激不足」だから
新しい刺激が少ないと、何をしても楽しいと感じられなくなります。
脳は新しいことに触れると「ドーパミン」という快楽ホルモンを分泌するのですが、同じことばかりしていると、この分泌量が減ってしまうのです。
例えば、最初はワクワクしたゲームでも、何時間もやり続けると飽きてしまうのと同じように、人間の脳は同じ刺激に慣れてしまう習性があるのです。
やらなきゃいけないと思うと楽しくなくなる
楽しむよりもやらなきゃ」という気持ちが強いと、気持ちが重くなって楽しくなくなります。
義務感が生まれてしまうとそれがプレッシャーとなってしまい、自然とやる気が失せるからです。
例えば、趣味として映画を観るのは楽しいのに、映画の感想を毎回書かなきゃいけないとなると、文章を書くのが好きな人であればいいですが、そうでない人であれば楽しさが半減してしまいます。
心や体が疲れている
何をしても楽しくないと感じるのは、心や体が疲れているのが原因である可能性もあります。
ストレスが溜まりすぎると、脳がエネルギーを温存しようとして興味ややる気を感じにくくなるからです。
例えば、忙しい日々が続くと、好きなことをする気力すら湧かなくなることがあります。
これは、脳が休んでほしいと訴えているサインなのです。
ストレスが体に与える影響についての詳細はこちらのサイトを参照してください。
Nike「ストレスが体に与える影響とその対処法」
無気力の原因は「やる気の待ちすぎ」
「やる気が出たら動こう」と思っているうちに、何もできずに1日が終わってしまった…。そんな経験はありませんか?
実は、無気力になってしまう原因のひとつは「やる気を待ちすぎること」にあります。
やる気は、じっと待っていても自然に湧いてくるものではありません。
では、どうすれば無気力のループから抜け出せるのでしょうか?
ここでは、そのメカニズムをまとめてみました。
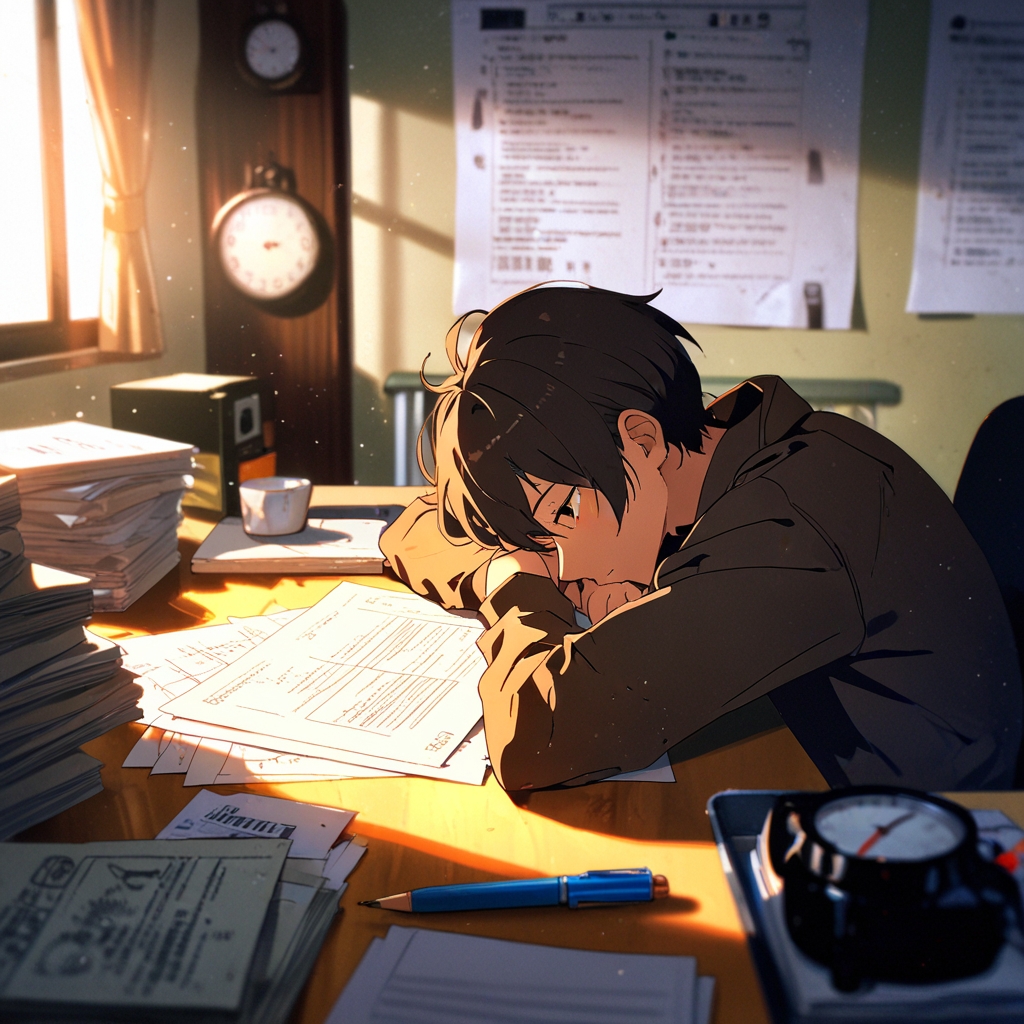
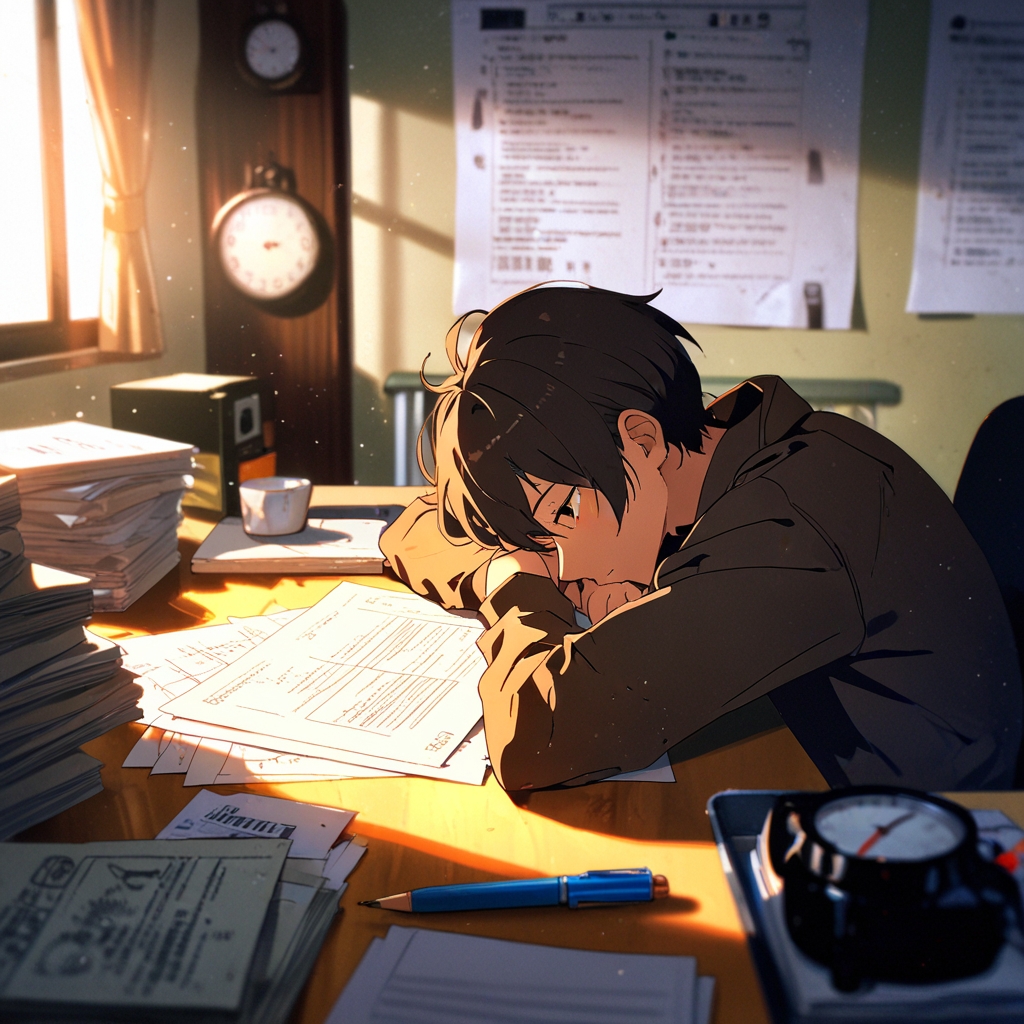
やる気は「出る」ものではなく「作る」もの
やる気は待っていても勝手に湧いてくるものではありません。
脳は行動を始めることで刺激を受け、少しずつ活性化します。
つまり、行動しなければやる気は生まれません。
たとえば、最初は気が乗らなくても、とりあえず5分だけでも手を動かしてみると、それ以降も集中して作業を続けることができることが多いのです。
行動とやる気との関係に関する詳細はこちらのサイトを参照してください。
神戸心理カウンセリングオフィス「「脳科学」から見た「やる気」の出し方」
完璧主義がやる気を奪う原因になる
最初から完璧にやろうと思うと、ハードルが上がりすぎてしまって行動できなくなります。
うまくできなかったらどうしようという不安が先に立ってしまい、行動する前から気力が失せるからです。
たとえば、絵を描いてみようと思っても「下手だと恥ずかしい」と考えてしまったら、ペンも持たずに終わってしまいます。
環境がやる気を左右する場合もある
やる気が出ないのは、環境が要因になっている可能性もあります。
人は、周囲の雰囲気や目に入る情報によって行動を決める傾向があるからです。
たとえば、机の上が散らかっていると勉強する気になりませんが、きれいに片付いた空間だと自然とやる気になることがあります。
何もしないのに疲れるのはなぜか
何をしていないのになぜか疲れるという経験をした方はいませんか?
身体を動かしていないのに疲れを感じると怠けているのかもと自己嫌悪に陥ることもあるかもしれません。
ですが、何もしないこと自体が疲れの原因となっている場合があるのです。
ここでは、その理由をまとめてみました。


頭だけがフル回転している
何もしていなくても、頭の中だけで考えすぎていると疲れが溜まってしまいます。
人は身体を動かしていなくても、心配事や不安を抱えていると脳が休まらずに、エネルギーが消耗してしまうからです。
たとえば、テスト前や大事な予定がある前日、体はしっかり休めたはずなのに、なぜか疲れが抜けないなんてことありませんか?
これは、脳がストレスを感じ続けているから起こるのです。
生活リズムの乱れが疲れを生む
不規則は生活は、自律神経を乱して疲れやすい身体を作ります。
睡眠時間がバラバラだと体内時計が狂ってしまい、常にだるさを感じるようになるからです。
たとえば、長期休みで昼夜逆転してしまったあと、学校や仕事が始まると異常に疲れることがあります。
これは、体が生活リズムを取り戻せずに、エネルギーを無駄に消費してしまうために起こるのです。
休むの意味を間違えている
ただダラダラと過ごすだけでは、心も体も本当の意味で休んだとは言えません。
疲れを取るためには、受動的な休み(スマホや動画を眺める等)だけでなく、能動的な休み(軽い運動や趣味)が必要です。
たとえば、長時間ベッドでゴロゴロしていても何となくダルいと感じることがあります。
一方、軽く散歩した後の方がスッキリすることが多いです。
これは、適度の活動が血流を促し、脳の疲れを取る効果があるからです。
能動的な休みと疲労回復の関係に関する詳細はこちらのサイトを参照してください。
東邦マッサージグループ「ゴロゴロ、ダラダラはダメ!積極的休養のススメ!」
趣味がない人でも無気力から抜け出すための小さな一歩


- 「とりあえず5分だけ」行動
- 気分が乗らない時でも行動を起こせる方法
- 楽しさを感じるためのシンプルな習慣
「とりあえず5分だけ」行動
やる気が出たら動こうと思っても、なかなか動けないのは先に述べたとおりです。
そんなときに有効なのが、とりあえず5分だけやってみるという方法です。
たった5分間の行動が、無気力から抜け出す大きなきっかけになることがあります。
ここでは、なぜ5分だけ行動することが有効なのか、その理由と具体的なコツをまとめてみました。


5分だけなら脳が抵抗を感じにくい
とにかくやると考えるとハードルが高くなってしまいますが、5分だけと決めることでそのハードルが幾分か下がります。
脳は大きな負担がかかることを避ける習性がありますが、短時間の作業であれば負担が少ないので抵抗を感じにくいのです。
ちょっと極端な例ですが、運動しようと考えると少し面倒に感じますが、1回だけスクワットしてみると考えればすぐにでもできそうだと思いませんか?
1回が2回になり、2回が4回、10回と増えていく。
小さな行動が、次の動きを引き出すきっかけになるのです。
5分続けるとやる気が出る
これは先ほどもお話ししたことですが、やる気は行動により脳が活性化した結果出るものです。
行動を始めることで、脳内の神経伝達物質が分泌されて、やる気を促す状態になります。
たとえば、掃除を始めると「ついでにここも片付けよう」と最初片付けようと思っていたところより片付けの範囲が広がっていき、結果的に部屋のほとんどの片付けが終わっていたという経験がある人も少なくないはずです。
「やる気」を待つのではなく、まずは5分間だけ行動してみましょう。
5分で終わってもOKだから気楽に取り組める
5分だけと決めることで気負わずに始めることができます。
5分でも長いなと思う方はもっと短くてもいいのです。
とにかく心理的な負担を軽減して行動するということが目的だからです。
たとえば、読書をしようとした場合、一冊読まなきゃと思うと億劫になりますが、5分だけ読もうと決めると意外と始められることが多いです。
5分が長いと思ったら3分でもいいし、時間設定がイヤであれば、前書きだけ読むとか目次だけ読むでもいいのです。
それも難しければ本をパラパラするだけでもアリです。
何でもいいのでとにかく始めましょう、行動しましょう。
気分が乗らない時でも行動を起こせる方法
ここまで読み進めてもまだ「どうしても気分が乗らない…」という方も多いはずです。
どれだけ「やろう」と思っても、気持ちがついてこないことはよくあります。
でも、気分が乗らなくても始められるコツがあるとしたらどうでしょう?
ここでは、やる気が出ないときでも無理なく行動を起こせる具体的な方法をまとめてみました。


「ながら作業」で気軽に取り組む
何かをしながら気軽に始めると、気分が乗らなくても行動しやすいことが多いです。
何かをやるための準備を意識すると面倒に感じますが、日常の行動に組み込むことでその負担を軽くできます。
たとえば、普段音楽を聴いたり動画を見たりしているのであれば、それをしながらストレッチをしたり部屋を片付けてみてください。
思いのほか作業がはかどるのを実感できるはずです。
手順を決めないでとりあえず手をつける
どうやるかを考えているとなかなか行動できないことが多いので、まずは適当に手を動かしてみましょう。
この適当というのが大事で、適当だからスムーズに進められることが多いのです。
たとえば、英語の勉強をはじめようと思ったのがいいが、どうやって勉強を進めようかと考えているうちにやる気が失せるという経験をした方は結構たくさんいるのではないでしょうか。
あれこれ考える前に、手持ちの参考書を読み進めてみましょう。
読んでみてこれでいいと思えばそのまま読み進めれば良し、ちょっと難しいとか簡単すぎるとか思えば新しいものを買ってくれば良し、ただ読むだけだと眠くなってしまうのであれば声に出して読んでみる、と言った具合に行動しながら軌道修正して理想のスタイルを目指せばいいのです。
「小さなご褒美」を設定する
脳は報酬を期待すると行動を起こしやすくなるため、「これをやったら好きなお菓子を食べる」といったようなご褒美を設定してあげると、自然と行動しやすくなります。
たとえば、勉強や仕事をする前に「終わったらこないだ買ってきたスペシャリティコーヒーを淹れよう」とか決めてスタートすると、不思議と作業がはかどるのです。
でも、ここでひとつ注意。
ご褒美の出し過ぎには気をつけてください。
一番最初に刺激に慣れてしまうと楽しさを感じにくくなるというお話をしました。
ご褒美を出し続けるとその刺激に慣れてしまい、動こうという気持ちが失われていく可能性があるからです。
楽しさを感じるためのシンプルな習慣
何かを始めてみることが大事なのはわかったけど、続かなかったらどうしようと考えている方も少なくないかと思います。
ちょっとした習慣を取り入れるだけで楽しさを感じやすくなる方法があるんです。
楽しみを感じやすくなるシンプルな習慣を知れば、日常の中で面白いと萌える瞬間が増えてくるかもしれません。
ここでは、無理なく楽しさを感じるための習慣をまとめてみました。


「結果」ではなく「過程」を楽しむ意識を持つ
うまくやることよりもやっている時間を楽しむことに意識を向けてみてください。
上達しないとか結果が出ないと思うと楽しさが半減しますが、とりあえずやることが楽しいと考えると続けやすいです。
たとえば、スポーツやゲームは最初からうまくできなくても楽しめます。
完璧を求めずに試している時間そのものが楽しいと感じることができれば趣味として長続きしやすくなるのです。
新しいことに少しずつ挑戦してみる
小さな変化を取り入れることで、飽きることなく楽しさを感じやすくなります。
同じことの繰り返しだと脳が慣れてしまい刺激が少なくなってしまいますが、そこに小さくてもいいので新しいものを入れることでドーパミンが分泌されて、また新たな楽しさを感じやすくなるのです。
たとえば、散歩をしているのであればいつも歩いている道とは違う道を歩いてみる、決まって頼むメニューがあるのであれば違うメニューを試してみるなど、小さな変化だけでも気分がリフレッシュして楽しさを感じやすくなります。
楽しそうな人の影響を受ける
楽しんでいる人の姿を見ると、自分もやってみようという気持ちになることがあります。
「ミラーニューロン」と呼ばれる脳の働きにより、人は他人の感情に共感しやすくなっているからです。
たとえば、友達が笑っているとつられて笑ってしまうことがありませんか?
同じように、YouTubeやSNSで楽しそうに趣味をしている人の投稿を見ていると自分もこんな風にやってみたいと感じやすくなるのです。
ミラーニューロンに関する詳細はこちらのサイトを参照してください。
Web LEON「出会うべき師とは、3年後の理想の自分を実現している人」
趣味と無気力についてよくある質問とその回答
最後に趣味がないことと無気力の関係についてまとめます
ここまでの内容を箇条書きでまとめます。
- 趣味がないと無気力になりやすいのは、新しい刺激が少なくなることで脳の快楽ホルモン「ドーパミン」の分泌が減り、楽しさを感じにくくなるためである。
- やる気は待っていても自然に湧いてくるものではなく、行動することで脳が活性化し、結果的にやる気が生まれる仕組みになっている。
- 無気力の原因には、完璧主義や生活リズムの乱れ、頭の中で考えすぎることなどがあり、環境を整えることがやる気を出す鍵となる。
- 気分が乗らなくても始められる方法として、「ながら作業」「手順を決めないでとりあえずやる」「小さなご褒美を設定する」などの工夫が有効である。
- 楽しさを感じるには、「過程を楽しむ」「新しいことを少しずつ試す」「楽しんでいる人の影響を受ける」といった習慣を取り入れるのが効果的である。
無気力な状態が続くと、「自分はダメなのでは?」と落ち込んでしまいがちですが、そう感じるのは決して珍しいことではありません。
趣味がないからといって、無理に何かを探そうとする必要もありません。
大切なのは、やる気を待つのではなく、小さな行動を積み重ねることです。
気分が乗らないときでも「とりあえず5分だけやってみる」「ながら作業で気軽に始める」「小さなご褒美を設定する」といった工夫を取り入れることで、自然と行動しやすくなります。
楽しさを感じるためには、新しいことに挑戦したり、結果よりも過程を意識することも有効です。
まずは、無理なくできることから始めてみましょう。
最初の一歩は小さくても、それが積み重なれば、大きな変化につながるはずです。